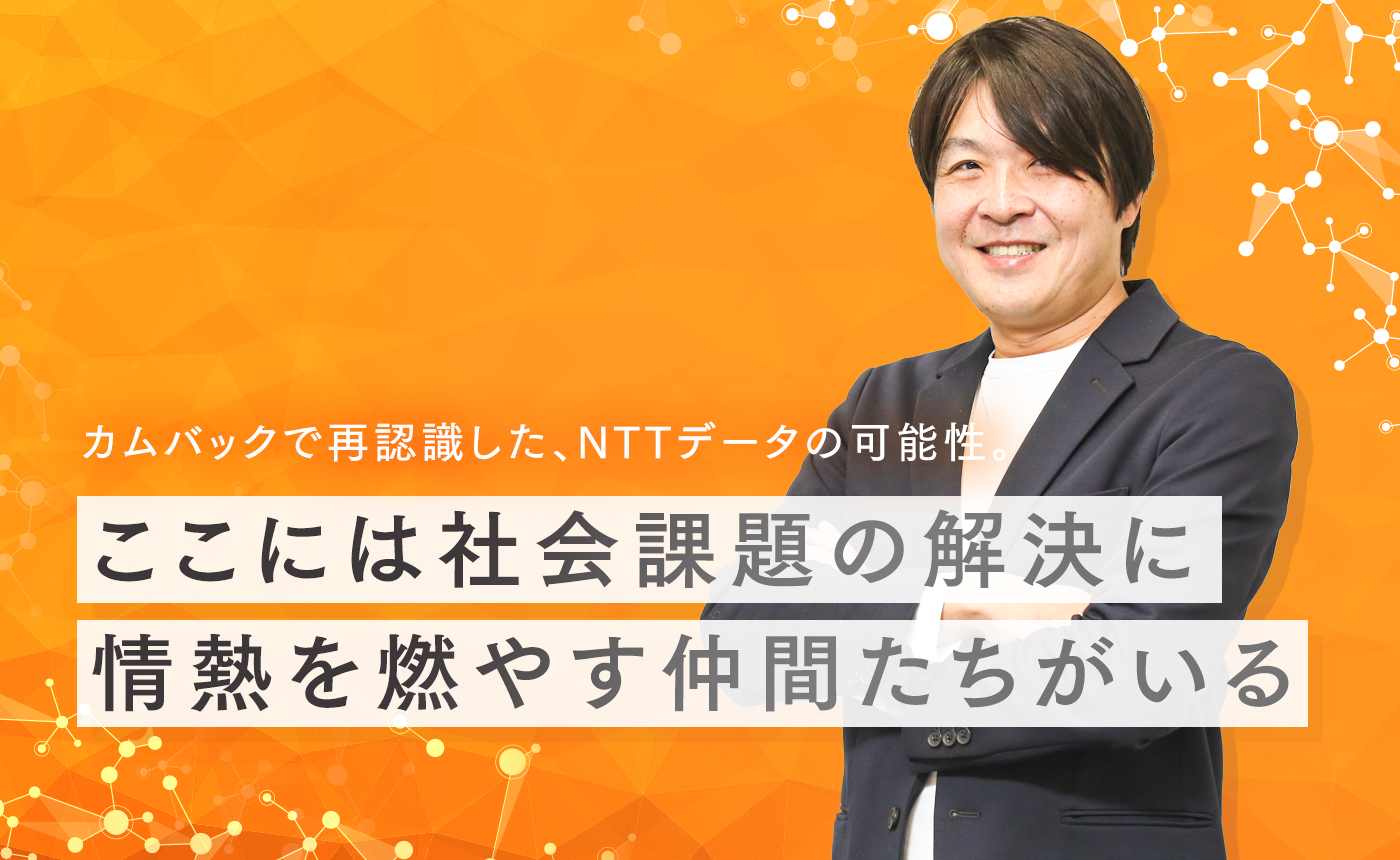医療系スタートアップでヘルスケア分野の課題解決に貢献

現在、コンサルタントとしてヘルスケア領域の社会課題解決に取り組んでいる三澤。新卒で入社したNTTデータから医療系スタートアップに転職し、経営企画部長として成長の基盤を築いたのち、再びNTTデータに戻ってきたバックグラウンドの持ち主です。
入社当初からコンサルティングというキャリアパスを志向していた三澤は、入社2年目から社会人大学院に通い、業務の傍らで勉強を続け、MBAを取得。その後はNTTデータ経営研究所に出向し、政府・金融関連の業務・組織改革を担当。NTTデータに戻ってからは、経営戦略、役員補佐としての組織マネジメントなどを経験しました。さらには日本電信電話(NTT)の経営企画部門にてNTTグループ横断の営業連携やブランド構築などに携わるなど、グループを横断して豊富な経験を積みました。
そんな中、三澤は知り合いの大学教授を通じて某大学発の医療系スタートアップと出会い、転職を決意します。そのスタートアップでは、運動機能が低下した人を対象としたブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の開発や製造を主なテーマとしていました。
順風満帆なキャリアを歩んできたように見える三澤は、なぜNTTデータを飛び出してまでスタートアップの環境に身を置くことを決めたのでしょうか。
それまでNTTデータを辞めたいという気持ちは一切なかったのですが、昔から社名や肩書を利用せずに仕事ができるようになりたいとは考えていました。
そのスタートアップ企業はまだアーリーステージにあり、社員もわずか数名のみ。経営状態はけっして盤石ではなく、事業の先行きも不透明。苦労しながらも、経営企画部長という立場で中期経営計画を作り上げ、シリーズCの投資ラウンドでの資金調達も成功。その後の事業拡大への下地を築きました。
事業を牽引する一方で、三澤個人としてはヘルスケア領域への関心を深めていきました。
人間の脳波や身体の動きをデジタル化するのは手探りの分野でしたし、正解のやり方がまだ存在しないところに面白みを感じました。加えてヘルスケア領域の大きな特徴として、困っている人に対してダイレクトに価値を届けられる点も私にとっては新鮮でした。
事業規模や組織も拡大したところで、三澤は次のフィールドを模索。そんな時、NTTデータのヘルスケア事業部に在籍する知人から声がかかりました。
ヘルスケアという社会課題に対して今後も何かしらの貢献がしたい、自分の力を活かしたいーー。そう考えていた三澤にとって、NTTデータはまさしく求める環境そのもの。ヘルスケア領域の課題解決という新たなミッションを胸に抱いた三澤は、再びNTTデータに戻ることを決めました。
プログラムに集ったのは社会課題の解決に情熱を燃やす仲間たち
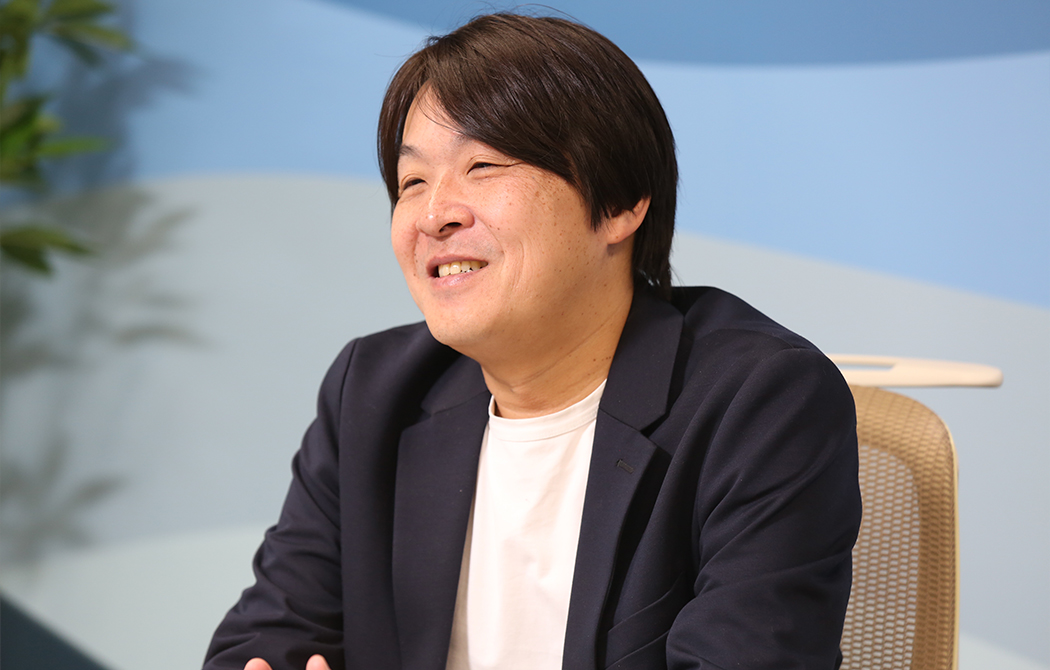
誰もが質の高い医療サービスを持続的に受けることのできる社会を実現する上で鍵を握るのが「公的医療データと民間健康データの融合」。NTTデータは「Harmonized Well-being with Data ~生活に溶け込む健康づくりが進む未来~」という未来像を描き、「公と民」を横断する形で社会課題の解決に取り組んでいます。
このような背景から、現在の三澤が所属するヘルスケア事業部では厚生労働省の医療情報プラットフォーム構想を支える部署とヘルスケア周りの様々なソリューションを扱う部署が両立しています。これらの「公と民」を掛け合わせ、シナジーを生み出す戦略立案が三澤に課せられたミッションです。
ヘルスケアの文脈では、国も大きく変わろうとしており、技術の進歩も目覚ましいものがあります。また、ヘルスケア業界のイノベーションは「シーズドリブン」ではなく「ニーズドリブン」で生まれるという傾向があります。だからこそ課題というものを真摯に捉えて解決策を作っていかないと誰にも使われないシステムになりますし、社会も良くなりません。
NTTデータはヘルスケア領域で様々なソリューションを展開しており、三澤がプロジェクトを推進している治験プラットフォームの「PhambieLINQ(ファンビーリンク)」もその一つ。ただし、社会課題解決のためには自分たちだけが行動するのではなく、多くの関係者を巻き込んで大きな動きを生み出すことが必要だと三澤は強調します。
国や研究機関、医療機関がバラバラの動きをしていては意味がありません。公的なデータと民間のデータを連携させることで、より良いヘルスケア社会が実現できると私たちは考えています。
そしてこれらの業務とは別に、三澤は2024年上期から開始した、社会課題ドリブンで新規事業開発に取り組むためのコンサルティング強化プログラムのメンバーに選出されました。以前からコンサル人財の重要性を認識していた三澤は、「とても良い施策なので、自分が選ばれたのは光栄だと思いました」と振り返ります。
プログラムで検討する新規事業のテーマは、各参加者が熱意を持って取り組める内容であれば自由。三澤はせっかくの機会だからと、あえて通常業務とは切り離したテーマを設定し、リサーチやディスカッションを行いました。
通常業務と並行してプログラムに参加するのは負担こそあるものの、次第に楽しんで取り組むようになったといいます。
私自身もそうですが、皆が楽しそうにディスカッションしている様子を見て、課題に対してソリューションを考えることが好きな人たちが集まっているんだな、と感じました。ビジネスパーソンとして優秀というだけでなく、社会に存在する問題を自分の力で解決したいというモチベーションを持っている人がこんなにいることに、改めて驚きました。
部署の垣根を越えて自分と同じような想いを持った人たちと出会えたことは、三澤にとって大きな収穫でした。NTTデータという会社の魅力を改めて知る機会になったといいます。
「我々がやるべき」という責任感で巨大な社会課題に挑む

プログラムは現時点でまだ進行中ですが、三澤は「地方都市の高齢化」に関するリサーチや事業検討などを経て、現在は認知症に対する問題の深堀りを進めています。認知症への対策については、「いかに早期検知できるか」と、「予後をデータで補足」することが重要だと三澤は語ります。
その両方ともITで実現が可能です。特に早期検知については、いまもいろいろな検知方法が検討されていますが、そう遠くないうちに抜本的な技術イノベーションが起こると考えられます。いずれ巨大なインパクトが社会にもたらされるはずですが、その時に自分たちが参加者の中にいなくていいのかと考えると、いても立ってもいられなくて。絶対に自分たちがやるべきだと思えました。
社会に変革が起こる時に、その当事者でありたいということ。「人がまだやっていないことをやるのが好きなのかもしれませんね」と三澤は自身のモチベーションを語ります。事実、三澤は前職のスタートアップでもBMIという世界で数社しか取り組んでいなかったテーマに挑んだという実績があります。
そしてNTTデータはたしかに大企業ではあるものの、けっして硬直的な組織風土ではなく、スタートアップに引けを取らない自由度の高さがあります。「ボトムアップで企画して、高い自由度を持って行動できるのは大きな魅力」と三澤は語ります。
さらには「産・学・官」を横断して多数のパートナーと連携できるからこそ、一社では実現が難しいような巨大なインパクトを持つ社会変革を実現できる可能性さえあります。
ただし、数ある社会課題の中でも特にヘルスケアという領域は広大であり、数年で成果が出るとは限りません。「芽が出るまで10〜15年はかかってもおかしくはありませんし、最終的に花が開くとも限りません」と三澤。それでも手をこまねいて見ているわけにはいかない重大な社会課題に対して、一体誰が挑戦するべきなのか。「我々がやるべきだと考えています」という三澤の言葉の裏には驕りはなく、公共・社会基盤分野で働く人財としての責任感と熱い情熱が渦巻いています。
社内外の多くの関係者を巻き込み、社会課題に一緒に向き合う仲間を集めながら、三澤たちはより良いヘルスケア社会の実現に挑戦し続けていきます。
―
今回はコンサルティング強化プログラムの参加メンバーのインタビューをお届けしました。本プログラムの参加者に限らず、NTTデータの公共・社会基盤分野には社会貢献に対する高い意識を持った人財が大勢集まっています。私たちは、社会課題解決に情熱を燃やす新しい仲間と出会えることを楽しみにしています。