NTTデータのグローバルビジネスを財務面から支える

Q.それぞれの仕事内容は?
 髙橋
髙橋
私はファイナンス担当として、NTTデータの事業計画の実現に向けて資金調達と配分の最適化に取り組んでいます。NTTデータがデータセンター投資への注力を進める中でコーポレートファイナンス機能の重要性は非常に高まっており、より高度化した機能が求められております。
 周
周
私は決算税務担当 税務グループに所属し、NTTグループとNTT データグループの国際税務関連業務を担当しています。具体的には、税務コンプライアンス対応や連結税効率の向上などがあります。現在は多国籍企業に対して全世界で最低15%の法人税率を課す「グローバルミニマム課税」に関する対応の比重が高くなっています。また、適切な税務処理を通じて節税効果を追求し、NTT データグループの収益を守るとともに、キャッシュアウトの軽減にも貢献して会社の価値向上に直接的に関われる点に、大きなやりがいを感じています。
 根岸
根岸
私はグローバル事業のガバナンスや戦略策定を担うNTT DATA, Inc. に所属し、ファイナンスチームの一員として働いています。主な業務はFP&AとNTTデータグループへのIR支援で、ファイナンスチームでは今年度から地域ごとに担当が分かれていることから、私は北米地域を担当しています。

Q.各チームの注力テーマは?
 髙橋
髙橋
私からは主に三つのテーマを挙げたいと思います。一つは金融費用の低減で、市場環境を踏まえて通貨・借入年限・金利条件(固定/変動)等のバランスを取りながら最適な資金調達方法を模索し実行することで、支払利息の低減を実現していきます。現在は、為替相場の変動も激しく、政策金利も大きく動いているような非常に難しい環境下にありますが、NTTデータの業績にダイレクトにインパクトを与えられる点にやりがいを感じています。
 周
周
会社に与えるインパクトが大きいからこそ、重い責任とやりがいを同時に感じられるのですね。
 髙橋
髙橋
はい。そして二つ目は有利子負債のコントロールで、NTTデータはこれまでにない積極的な投資を行っており、それに伴い借入額も増加していることから、財務健全性の確保も重要なテーマとなっています。そして三つ目として、三社体制下※における資金ガバナンスの強化があります。ビジネスを強く後押しするようなトレジャリー機能の配置や安定実施は事業運営上不可欠ですが、NTTデータグループ、NTTデータ、NTT DATA, Inc.の三社それぞれで置かれている状況が大きく異なることからさまざまな観点での検討・対応が求められます。
※2023年7月より、NTTデータは持株会社であるNTTデータグループ、国内事業会社であるNTTデータ、海外事業を統括するNTT DATA,Inc.の3社体制に移行しています
 根岸
根岸
NTT DATA, Inc.の場合、グループの変革期の中で生まれた会社であり、現在も進化の最中にあります。直近の変化の例としては、それまで海外子会社ごとに行っていた管理会計を地域別に見るようになったことが挙げられます。その狙いには地域ごとの業績管理と管理会計の連動があり、グローバルの事業戦略とも密接に紐づいています。ただし、地域ごとの特性を捉えるのは簡単ではなく、それぞれの地域の状況や事業の戦略、為替レートの変動なども考慮しなければいけません。現地の会社にも実際のビジネスの状況をヒアリングしながらキャッチアップするように心掛けています。
 髙橋
髙橋
私はシンガポールに出向していた時期があるのでよく分かりますが、グローバルといっても地域ごとに置かれている状況はまったく異なりますよね。周さんはどうですか?
 周
周
私の場合は、やはりグローバルミニマム課税の対応が大きなテーマです。令和5年度の税制改正でグローバルミニマム課税が導入され、これまではドライラン(予行演習)を実施してきましたが、今年度から本格運用が始まります。この制度では、税率が15%未満の国がある場合、その不足分は親会社のNTT持株(日本電信電話株式会社)に課税されることになります。このグローバルミニマム課税は経済協力開発機構(OECD)の「BEPS包摂的枠組み」において合意された制度ですが、各国でルールの準拠状況などが違うところがあるため、日本をはじめ、各国の対応状況等を調べるところから始める必要があります。
 髙橋
髙橋
それぞれに状況が違う各国の税制を網羅的に理解するのは、非常に大変そうですね。
 周
周
はい。NTT持株主導のプロジェクトではありますが、NTTグループの中でもグローバルビジネスの中心はNTTデータグループが担っていることもあり、私たちが国ごとに実効税率を計算するために海外子会社から情報を収集し、取りまとめてNTT持株に報告を行っています。情報収集は個社別で行っていますが、国別報告書(CbCR)については欧州では情報開示の要請があるなど、地域によって対応状況が異なってきます。開示する以上は情報の正しさを担保したいと考えていますが、複雑なルールであるため、すべての海外子会社が正確に報告できることを担保するため、海外子会社とも密接に連携しながら取り組んでいます。
国内では得られない経験を積み、成長を実感できたエピソード
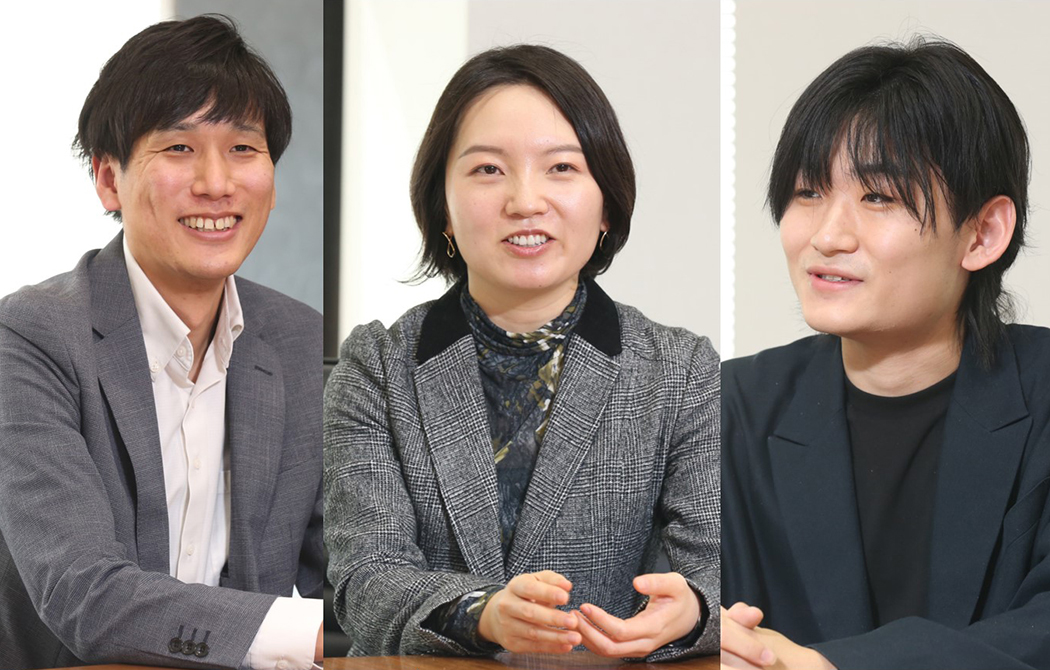
Q.印象に残るエピソードは?
 髙橋
髙橋
私は、シンガポールのNTT DATA Asia Pacificに出向していた時のことが印象に残っています。着任したばかりの頃は、定期業務も決まっておらず、自分自身で業務を作っていく必要がありました。また、当時の上司はシンガポール人で、カウンターパートとなる各グループ会社のメンバーもAPAC域内各国のローカルスタッフであったため色んなバックグラウンドやカルチャーを持った方々と仕事をする必要がありました。皆フレンドリーでよい人たちではあったものの、本社から来たばかりで何者か分からない人にはグループ会社のメンバーも十分な情報はくれませんし、上司もどんな仕事を任せればよいのか分かりません。自分が何者で、何ができるのかを周囲に示していくことが大切でした。また、言語や文化の壁にもぶつかり、最初は思うようなパフォーマンスが全然出せませんでした。
 根岸
根岸
私も自分の業務を通じて国による価値観や状況の違いは実感しています。そこからどのように壁を乗り越えたのですか?
 髙橋
髙橋
まずは、現地のメンバーが対応できておらず、かつ自分のこれまでの経験や知識で貢献できるものは何があるのかを考えながら、少しずつ自分のバリューを発揮していきました。価値観の違いについても、日本人のように行間を読み取ってくれることはないので、しっかりと言葉にして意思疎通を図って確認しながら着実に仕事を進めていくようにしました。また、日本の本社からの依頼事項が上手く伝わっておらず、現地のメンバーたちが「これってどういうこと?」と悩んでいることも多いことに気づき、先回りして私が間に立って動くことも多々ありました。
 周
周
主体的に自分の価値を示しながらメンバーとの信頼関係を築いていったのですね。知識やスキル面でもいろいろなチャレンジがあったのではないですか?
 髙橋
髙橋
その通りです。その時はアジア地域統括会社の財務部として、域内のグループ会社の実行管理(管理会計)から資金関連業務、決算報告対応(財務会計)、グループ運営費配分プロセスの設計、経営状態の厳しいグループ会社に対するハンズオンサポート等、幅広い業務を担当していました。それまでの私は、会計制度とIRしか経験しておらず、その他についてはあまり詳しくありませんでしたが、それでも幅広い領域について最低限の知識は持つ必要がありました。多岐にわたるさまざまな業務を経験する中で都度キャッチアップしていき、結果として自分の知識の幅を広げることができましたし、現地メンバーからの信頼も得ることができ、有益な経験が積めたと感じています。
 周
周
私の印象に残るエピソードとしては、中国における譲渡益課税の対応があります。NTTデータグループは2022年に海外組織再編を実施しましたが、当時の中国ではコロナ禍における「ゼロコロナ政策」の影響から、現地の税務署のシャットダウンや厳しい入金審査、厳しい申告期限などのさまざまな課題がありました。現地の税制を理解するだけでは対応しきれない点に難しさがありました。
 髙橋
髙橋
こちらが現地の税制やスケジュールに則って申告しようとしても、それ以外の予測できない問題が発生するということですよね。
 周
周
はい。それでも申告が遅れるとペナルティが発生してしまいます。想定されるリスクは多岐にわたりましたが、それでもすべてのリスクを見据えて社内外の関係者と調整を行いました。タイトなスケジュールでありながら、一つミスがあったら次に進めない、という緊張感の中、関係者同士で一丸になって取り組んだことで、どうにか期限内の申告と納付を完遂できました。

 髙橋
髙橋
それはやり遂げた時の安堵感が大きかったでしょうね。根岸さんはいかがですか?
 根岸
根岸
ファイナンスチームでは今年度から地域単位で海外子会社の財務を管理するようになり、私は北米地域を担当するようになりました。ドイツの子会社を担当していたことがありましたが、北米地域のビジネスを見るのは初めてだったので、それまでの業務との違いに驚きました。現担当では四半期ごとの決算発表に向けて経営幹部向けに北米地域の業績状況や投資家・アナリスト向けの資料を作成する際、最初は上司レビューで指摘が入ってばかりで。いかに自分が現地の状況を理解できていないかを痛感するばかりでした。
 髙橋
髙橋
現地のビジネスを理解していないと納得感のある説明資料は作れませんよね。
 根岸
根岸
はい。北米地域の業績を経営幹部に報告するにしても、投資家・アナリスト向けの資料を作成するにしても、まずは地域の状況をしっかりと把握し、そして現地の会社やビジネスのことも理解していなければいけません。周囲の先輩方にサポートしていただきながらも、現地のことを理解するように努めることで、徐々に私が分析した北米地域のビジネス状況が経営幹部に報告されるようになっていきました。
 周
周
どんどん説明資料のレベルが上がっていったのですね。苦労が多かった分、成長も実感したのではないでしょうか。
 根岸
根岸
そうですね。少し細かい話をすると、四半期ごとの決算発表はタイムラインがタイトで現地からの説明資料が出てくるのが終盤になるため、まずは数字だけである程度の分析を行っておくことが求められました。現地の状況をあらかじめ理解しておくことで、数字だけで一定の分析ができるようになり、その分析をもとに現地にヒアリングしながら資料に反映していきました。もちろん上司やチームの助けもありましたが、自分の成長を実感できたのは嬉しかったですね。
国や業務の領域を超えて、「やりたい仕事」が必ず見つかる場所

Q.NTTデータの財務部で働く魅力は?
 髙橋
髙橋
今回集まったメンバーは同じ財務部とはいえ全員違う仕事をしていますよね。それだけ仕事の幅が広く、チャンスが多いということだと思います。私が入社した時から振り返ってみても、会社の事業や体制はどんどん変わってきていて、財務部で求められるスキルセットも大きく変わってきていると感じます。変化が激しい分、成長のチャンスは本当に多いと思いますね。NTTデータの場合は海外事業も大きく拡大していることから、より一層幅広い経験を積める可能性があります。
 周
周
やりたいことに挑戦できるチャンスの多さは私も感じています。グループの経営戦略に則った施策であれば、主体的に挑戦することも可能です。以前、私は同一グループ内で損失を課税ポジションの姉妹会社に譲渡できるイギリスのグループリリーフ制度に着目し、同じようなルールが他の地域にもあるのではないかと考えて調査したことがあります。シンガポールにも類似の制度があることが分かって上司に報告したところ、現地に出張してグループ会社に説明する機会を得られました。自分自身の手でプロジェクトを作ることができて、仕事の手応えを感じました。
 根岸
根岸
私は想像以上のグローバルな仕事に挑戦できる点に魅力を感じています。私の入社前のイメージでは、NTTデータはグローバル企業だとはいっても日系企業であり、特に財務は「数字が言語」のようなところもあるので、そこまで英語を使う機会はないだろうと思っていました。ですが、入社後はNTT DATA, Inc.に配属され、多くの国の方々と英語でコミュニケーションを取っています。本当にグローバルな会社なんだと改めて思いましたね。
Q.NTTデータのカルチャーは?
 髙橋
髙橋
皆さんの話からよく分かるように、NTTデータの風土として、新しい仕事にチャレンジできる機会が豊富にあります。もちろん本人の努力は必要ですが、同じことをやり続けるというよりは、新しいことに挑戦して成長したい人には素晴らしい環境だと思います。実際、私自身もシンガポールへの出向は自ら希望して実現しました。日本にいた時よりも大きな負荷はかかりましたが、自分のスキルを高めることができました。もともと私がNTTデータに入社した理由の一つにも、グローバルな仕事が経験できる会社、という点がありました。その時の希望は実現していますね。
 周
周
同感です。実は私の最初の配属はERPパッケージの開発・マーケティングでした。まったくの異分野から財務部に異動できたという事実も高橋さんのお話を証明していると思います。国内外を問わず、必ず自分のやりたい仕事が見つかり、挑戦できる、という点はNTTデータの大きな特徴です。
 根岸
根岸
NTT DATA, Inc.のカルチャーという点でいえば、やはりグローバルが挙げられます。NTT DATA, Inc.のFP&Aのトップも外国籍ですし、周囲の仲間や関係者たちの中には現地で働く外国人の方も多く、世界中の仲間たちと一緒にグループを支えていることを実感します。
 髙橋
髙橋
加えて、NTTデータ全体に共通する話ですが、自分の仕事に対して誠実な人が多く、最後までやり遂げるマインドを持った人が多いのは財務部においても同じですね。
 周
周
はい。私の周囲の仲間たちも、国籍を問わず、信頼できる人たちばかりだと感じています。NTTデータのカルチャーの土台には信頼関係を大切にする価値観があると思います。
 根岸
根岸
チームワークはNTTデータの強みによく挙げられますが、周さんがおっしゃったように、仲間同士の信頼関係が根底にあるからなんでしょうね。

Q.座談会の感想や気づきは?
 髙橋
髙橋
全員違う業務を担当しているからこそ、なかなか生の声を聞く機会はありませんでした。とても勉強になりましたし、NTTデータの財務部の魅力を改めて発見することができました。
 根岸
根岸
確かに皆さん違う業務を担当していますが、一方で共通する話も多かったのが印象的でした。違うことをしていても、実は同じことを考えながら仕事をしている、と知れたことは収穫でした。
 周
周
財務部の中では異なる担当間で連携する機会もあります。コロナ禍以降はリモートワークが多かったのですが、実際に対面で話を聞けたことで今後の連携もしやすくなると思いました。
 髙橋
髙橋
確かにそうですね。今回の座談会は、財務部内のチームワークをより一層強くするきっかけになりそうですね。
—
経営への貢献やスキルアップにフォーカスした前編に続き、後編となる今回では「グローバル」にフォーカスして財務部の魅力をお届けしました。六人六色の業務内容から、NTTデータの財務部で多種多様な経験が積めることが伝わったのではないでしょうか。財務パーソンとしてのさらなる高みを目指したい方にとって、NTTデータの財務部はチャンスに溢れた絶好の舞台です。




