- 目次
7つの観点から読み解くSDVがもたらすインパクト
NTTデータは、ITサービス事業者として、さまざまなインダストリーの構造変化、ソフトウェアデファインドによるコンピューターシステムの変遷に関わってきた。その経験、知見から、自動車業界で注目されるSDVをどう捉えているのだろうか。
一般的なSDVの解釈の一つは、「販売後もクルマの機能を増やし、性能を高められるクルマ」だ。その解釈を踏まえつつ、「SDVは、ユーザー起点で新たな体験価値を提供し続けるエコシステムと捉えることができるのではないか」と提言するのは、NTTデータの取締役副社長、有馬勲だ。「SDVが実現された世界では、従来のクルマの価値である“移動”だけでなく、クルマと、その外の世界がリアルタイムに繋がることで新たな体験価値を提供できるようになります。事業者同士が連携することで、クルマから発生するデータをさまざまな領域のサービスやモノと掛け合わせ、エンターテインメントや買い物を楽しんだり、ヘルスケアへと活用したりする未来があります」と続ける。
NTTデータ入社後、研究開発部門を経て、小売・流通・サービス業、製造業向けITサービスに従事し続けてきた有馬。幅広い業界に携わってきた経験から、SDVが自動車業界にもたらすインパクトを7つの観点で見ているという。
1つ目の観点『エンドユーザーとの関係性』
有馬は「デジタル化以前、エンドユーザーが重視していたのは機能や性能、コストでした。その結果、マテリアルやメカの変化・進化が競争の起点となってきました。一方、デジタルの時代では、デジタルテクノロジーの進化と、既知のものと組み合わせにより、新たしい価値が創造されています。また、従来であれば、自社開発で特殊技術を使っていれば、その模倣困難性が高かったわけですが、現在は、変化への対応スピードの方が重要になっています」と指摘する。それ以外にも、下図のような変化が顕著に表れている。

図1:エンドユーザーとの関係性
有馬は変化の具体的な事例としてHUAWEIの取り組みを挙げる。
「HUAWEIは元々、通信機器などを提供していた製品中心の企業でした。しかし現状は、スマートフォンに採用していた独自OS『HarmonyOS』を、パソコンやスマートウォッチ、テレビ、そしてクルマなどへ広げ、ライフスタイル全体を提供する総合サービス企業へと変化しました。たとえばクルマでは、生活空間の延長線と定義し、冷蔵庫機能やエンタメ、フルフラットな後部座席などでくつろげる空間を演出しています。自動車業界も、エンドユーザーへの提供価値を継続的に変化させていく必要があるのではないでしょうか」(有馬)
2つ目の観点『ビジネスモデルの多層化』
これまで自動車業界のビジネスモデルは、クルマ自体の販売が中核だった。いわばハード中心である。それが最近では、AD(自動運転)やADAS(先進運転支援システム)の普及により、それらソフトウェア機能の販売なども始まっている。
「今後は、ソフトウェアの販売、ソフトウェアから派生するデータをもとにしたサブスクリプション型サービスの収入など、ビジネスとしての儲け方の選択が増えていく可能性があります。これまでのクルマをハードウェアとして販売することに加えて、ソフトウェアの販売、データの活用・販売へと、ビジネスモデルの多層化が加速していくと予想しています」(有馬)

図2:ビジネスモデルの多層化
NTTデータは、すでにデータを活用したサービスに向けた取り組みを始めている。それが、kmタクシーと共創する『運転特性データを活用した脳の健康状態を推定するアルゴリズム構築の実証』だ。詳細は、2025年1月17日付のリリース(https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2025/011701/)や記事(https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2024/0301/)に詳しく記されているのでご一読いただきたい。
3つ目の観点『ソフトウェアが競争優位性の中心』

NTTデータ 取締役副社長
有馬 勲
この10年ほど、サーバーやネットワーク、ストレージといったハードウェアを仮想化技術で抽象化し、これらのコンピューターリソースをソフトウェアによって制御しようというSDx(Software Defined Anything)という考え方が主流になりつつある。
「クルマでも、ソフトウェアがハードウェアを全面的にコントロールしたり、機能を変更したりする時代が訪れてきています。当然、ハードウェアそのものの意味合いが薄れることはありませんが、コンピューターシステムのパラダイムシフトであった仮想化が自動車業界にも大きな影響を与えるでしょう」(有馬)
4つ目の観点『オープン化』
「オープン化」もコンピューターシステムにおけるパラダイムシフトの一つ。ソフトウェアやハードウェアの仕様を公開することで、異なる開発者同士で互換性を持った製品開発が可能なオープンアーキテクチャもその1つである。
「オープン化の中でも重要な概念は、オープンソースです。コンピューターシステムの世界では20~30年前からあるのですが、当時は可用性が高いシステムには使えないという否定的な声も少なくありませんでした。しかし、今ではオープンソースなしにシステム構築はできないと言っても過言ではありません。無理だと思っていることでも、時代の進化によって当たり前のことになるのです。“クルマには高い安全性が求められるので、オープンアーキテクチャは難しい”という意見もありますが、そこをクリアできれば新しい価値創造につながるはずです」(有馬)
5つ目の観点『「抽象化」による再構築』
有馬は、設立後まだ間もない頃のインテルの事例を挙げ、「もともと個別であった要件を、 1つの目的として抽象化して考え、そしてその目的に対して再構成する考え方でインテルはマイクロプロセッサを生み出しました。この考えは、現状の自動車業界でも起こっているし、今後はさらに加速すると思います」と語る。

図3:インテル事例
「顧客体験を起点にクルマの提供価値を再構築すれば、クルマが持つそれぞれの機能に対して新しい使い方が出てくるかもしれません。たとえば、各機能を抽象化・汎用化して、APIで呼び出せるようにすれば、さまざまな階層を超えた利用が可能になり、新たな顧客体験価値を生み出せるのではないでしょうか」(有馬)

図4:「抽象化」による再構築
6つ目の観点『ビジネスと技術開発の一体化』
「クルマの販売後も顧客体験をアップデートし続けるためには、これまでのようにクルマ作りが直列的に行われるだけでは実現できません。開発に携わるさまざまな技術組織が連動してすぐにアップデートができるようにする組織構造が必要になります。顧客体験を最大化するため、ビジネスの目的に対して技術開発が一体化する必要があるのです」と有馬は指摘する。

図5:ビジネスと技術開発の一体化
7つ目の観点『企業の組織運営』
自動車産業の競争力の源泉は『Tier構造』にあった。細分化された役割分担の中で、先行開発と量産化できる組織・業界構造を持っていること、ハードウェアの圧倒的な先進性・安全性を中心とした品質を作り込めること、そして、PHEV(プラグインハイブリッド車)やEV、ICE(内燃機関車)など多様な車種を開発で培ってきたハードウェアアセットを再利用することによるコスト競争力などが強みだった。
「これから自動車業界がめざすべき企業運営では、(1)業界内外の垣根を超えたエコシステムの確立と新しい競争原理に沿ったマネジメントモデルへの変化、(2)メカトロニクス・エレクトロニクスだけでなく、ソフトウェアや顧客体験のデザインなどケイパビリティを継続的に拡張する、(3)業界内外を超えたエコシステム全体の中で自走するための高速オペレーション技術の実装、この3つの観点が重要です」(有馬)
そして、エコシステム確立に向けて「ここまでわたしが示したことだけでは、エコシステムを構成するのに十分ではありません。この7つのインパクトに対して、いろいろな企業の皆さんと一緒になって新しいオープンな取り組みをしていくことがエコシステムに実現に繋がると考えています」と展望を語る。
ソフトウェア領域でデンソーとNTTデータが共創する理由
有馬が企業運営で提唱した3つの観点。この観点をもとに、NTTデータはデンソーとソフトウェア領域での包括提携を締結している。両社の戦略・人材・技術の協力関係をさらに深化させ、日本の自動車産業の発展や、社会課題解決への貢献をともにめざすことが目的だ。
デンソーは2030年を見据えた長期方針のスローガンに『地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。』を掲げており、その上で、環境面では2035年カーボンニュートラルを、安心面では交通事故・死亡者ゼロをめざしている。デンソー モビリティエレクトロニクス事業グループ長の近藤浩氏は、「質の違うエンジニア同士が混ざり合うことで、SDVの実現にどうスピード感を持たせられるようになるのか楽しみです」と期待を寄せる。

株式会社デンソー モビリティエレクトロニクス事業グループ長
近藤 浩 氏
「自動車業界は100年に一度の大変革の真っ只中にあります。その要素のひとつであるSDVをスピーディーに成し遂げることは非常に重要。そのためにも、エンジニアの思考、マインドを変え、顧客体験起点でのサービス・システム開発によって価値を生み出せる会社にならなければいけません」(近藤氏)
SDVの登場により自動車業界以外の企業の参入も増えることだろう。CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー:世界最大のテクノロジー見本市)ではその傾向が顕著に見られ、さまざまな企業が顧客体験の一部として自らのブースにクルマを展示していた。実際にCESに参加した近藤氏は、このように感じたという。
「社会システムを構築する企業、それを成立させるシステムをつくる企業、システムを制御する機器を作る企業、その機器に入っている半導体をつくる企業、さまざまな企業が独自にSDVを解釈し、新しい発想で展示をしていました。これだけ多種多様な企業をひとつにまとめるためには、企業が提供するサービスやハードをつなぐインターフェースとそれを成立させるアーキテクチャが重要です。そして、このつなげる手段としてのソフトウェアが果たす役割は、ますます大きくなると感じました」(近藤氏)
100年に一度の大変革期で求められる組織の在り方
100年に一度の大変革期で、さまざまな企業が参入してきている自動車業界。求められるのは変化のスピードだ。しかし、人の命を乗せて走るクルマの性質上、自動車業界は完璧な品質を求めるため、スピード感を持った対応が難しい傾向がある。近藤氏は「まずは、小さなものを早く回すトライアルから始め、スピード感を持って取り組む環境を会社のなかに広めたいと考えています」と語る。
一方のソフトウェア業界は、アジャイル開発の普及によりスピーディーな開発も増えている。アジャイル開発は、適用しやすいCX(カスタマーエクスペアリエンス)領域から始まった。クルマでも同じように、スピーディーな開発ができる部分があるはずだ。近藤氏も「レイヤーによって品質レベルの考え方を変える必要がある」と考えを述べる。
「安全に関わらない部分では、最後の1%を完璧に仕上げるために長い時間をかけるよりも、まずは世に出して、何かあればスピーディーに修正を行う。特にSDVでは、その考えが求められるでしょう」(近藤氏)
「もちろん、一瞬でも止まってはいけないシステムでは完璧が求められます。場合によってはスピーディーに取り組む案件は組織を分けて、既成概念がない状態で開発を進めていく方法もあります」と有馬。NTTデータでも品質を重視するシステムとスピード感を重視するシステムで組織を分け、両組織でエンジニアを循環させ、人材育成につなげる取り組みもしている。
デンソーとNTTデータで生み出す新しい価値で社会に貢献
ソフトウェア領域での包括提携を締結したデンソーとNTTデータ。ハードウェアとソフトウェアの違いはあれど、エンジニアは自分たちがこれまでやってきたことを「聖域」と捉えることもある。近藤氏は「これからは聖域に閉じず、オープンにつながっていくことが大事。デンソーとNTTデータの仕事のやり方は異なりますが、そういった会社同士でシナジーを出しながら、しっかり社会に貢献していきたいと思います」と語る。
有馬も近藤氏の言葉に「価値観や文化の違いはあります。しかし、それは二項対立でどちらが正しいという話ではありません。AとBがあれば両方取りに行く、そして、AでもBでもない新しい価値観をつくっていくことが重要です」と賛同した。
「重要なのは、その人の価値観に沿った仕事ができる環境。深く突き詰める人も大事だし、それを上手くつなげることを考える人も大事。このとき、自分と違った価値観の人に拒否感だけは持ってはいけません。そのために、組織を率いる立場の人間には、しっかりとしたガイドが求められます」(有馬)
新しい価値観で、デンソーとNTTデータは、自動車業界が迎える100年に一度の大変革期に挑み、顧客起点の新たな価値をモビリティに提供していく。

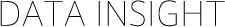



ホワイトペーパー「NTT DATAが考える自動車業界の変革と新市場」についてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/industries/mobility/
あわせて読みたい: