- 目次
こんにちは。
NTTデータの“City Life Experience”という、都市空間における体験、まちづくりに関わる取り組みを行うチームでコンサルタントとして活動している長崎(ながさき)です。
皆さまは「経済や効率だけでは測れない、私たちが本当に求める都市の魅力」について考えたことがあるでしょうか?
都市開発において、経済性や効率性が長らく重視されてきましたが、都市の本質的な魅力は、そこで感じる「感情」にこそ宿っているのではないでしょうか。特に東京のような大都市では、日々の忙しさの中で、心地よさや驚きといった感情的な要素が都市空間のデザインにおいて重要な役割を果たしています。しかし、こうした感情価値は数値化しにくいため、見過ごされがちです。本ブログでは、都市体験のデザインスタジオ「for Cities」が、三菱地所が主催するアーティスト×企業の協働から新たな可能性を拓く「有楽町アートアーバニズム(YAU)」と共に実施した「Urbanist Camp Tokyo 2024」での活動を紹介しながら、プログラムを通じて感じた感情価値を指標化し都市開発に活かす可能性についてお話ししていきたいと思います。
1.URBANIST CAMP TOKYO 2024とは?
Urbanist Camp Tokyoは、多様な背景を持つ人々が集い、都市の未来を創造するためのスキルを学び実践する3か月間のプログラムです。都市計画の専門家でなくても、座学と実技を組み合わせたカリキュラムを通じて、複雑化する都市の課題に対応する知識と経験を身につけます。
参加者は「都市の暮らしを創造していく人=アーバニスト」として、都市の可能性を探求し、主体的に都市生活を楽しむための能力を培います。
前年度は「都市の再野生化」をテーマに実施されました。今年度のURBANIST CAMP TOKYO 2024はEmotional City -都市の感情価値-をテーマに実施され、東京・大丸有エリアを舞台に、都市空間における「感情価値」を再発見し、合理性や経済性とは異なる切り口での都市のあり方について考えます。
プログラムは3つのステップに分けて進められ、まずは取り組みの解像度を上げるために、有識者のレクチャーやワークショップを通じた事前インプットを行いました。次に、事前インプットでの学びを活かしてチームに分かれて都市における感情価値に関する調査、調査結果の可視化に向けたアイディエーションを行い、最終的にチーム毎の最終成果物作成という進め方で行われました。
アイディエーションのフェーズでは、10代~30代の20名のアーバニストが5つのチームに分かれ、都市空間がどのように私たちの感情に影響を与えるかを探りながら、新たな都市の魅力を発見していきました。各チームは都市の感情価値という大テーマの中でも異なる切り口で都市の感情価値について調査していきました。
各チームの最終成果として、感情価値に関する調査レポートである「Emotional City Guide」と、都市の感情価値を体感してもらう「Emotional City Tour」が制作されました。Emotional City Guideでは、感情価値を地図に落とし込み、特定の場所が引き起こす感情を視覚的に⽰しています。また、Emotional City Tourは、実際に都市空間を歩きながら感情価値を体験するガイド付きツアーです。
- ※前年度取組

2.レクチャー:関係性と身体性から見た都市の新しい評価指標
レクチャーでは、社会学者の山田陽子様、ライフルホームズの島原万丈様、データ可視化の実務家の矢崎裕一様、アーティストの木原共様等、様々な領域の有識者のレクチャーをもとに、都市の感情価値に対する理解を深めました。山田様による社会学の観点から都市の課題や価値に関して評価する手法の話や、島原様の都市を経済価値以外の指標で測る手法に関する話から、都市における感情価値の重要性についての理解を深めました。
島田様が指摘された、日本の都市が快適で便利である一方で、「面白さ」や「楽しさ」が見落とされがちな課題は印象的で、感情価値に注目する本プログラムと深く関連しました。例えば、豊洲の道路についての説明では、広々と整備された道路が車にとっては理想的である一方、歩行者の楽しさを損なうデザインが多い点が考えさせられました。また、チェーン店の増加による消費体験の均質化が、地域の個性や独自の魅力を失わせている現実も浮き彫りになりました。

レクチャーで言及された豊洲の道路
こうした現状を受けて、島田様は「都市を評価する視点を経済価値だけにとどめてはいけない」と指摘されました。その都市で人々がどんな体験をし、どんな感情を抱くのか。これを測ることが、これからの都市づくりには欠かせないといいます。そのために提案されたのが、「関係性指標」と「身体性指標」という新たな視点です。
関係性指標では、地域とのつながりを感じられることがカギとなります。ただ人が集まるだけでなく、匿名性やプライバシーを守りながら他者と交流できる場の重要性、そして偶然の出会いやロマンス、自己実現の機会など、人々の心を動かす要素が評価の基準に含まれるべきだと語られました。
一方で、身体性指標は、都市を「身体で感じる」という視点を提供します。地域独自の食文化や自然といった感覚的な体験、さらには歩くことそのものを楽しめる環境づくりが都市の魅力を形づくるといいます。
これらの視点は、私たちが普段見落としがちな都市の本当の価値を再発見させてくれます。都市がただ便利なだけではなく、人々の感情や体験に寄り添う場となるためには、何が必要なのかを考えさせられる内容でした。レクチャーを通じて、都市を評価する際に経済価値だけでなく、感情価値や体験価値を含む多面的な視点が不可欠であることを改めて学びました。この視点は、私たちが進めている「Urbanist Camp Tokyo 2024」の取り組みにも通じるものがあり、都市空間に新たな魅力を見出す重要なインプットとなりました。
3.チームテーマ:都市の中の感情の避難所(Asyl)を求めて
このプログラムでは、参加者たちは5つのチームに分かれ、都市が引き起こす多様な感情の中から特定の感情に焦点を当てて考察を深め、そのテーマに基づいて調査を進めました。
その中でも私たちのチームでは「労働空間での感情の扱い」に課題を⾒出し、調査を進めていました。
大丸有エリアは日本を代表するビジネスエリアであり、効率性と合理性が強く求められる場です。ワーカーを対象としたプレアンケートの結果では、「大丸有エリアは働く場所なので、感情は動かない」という声が多く聞かれました。このことから、「労働空間で感情が抑制されがちである」という仮説が立てられました。
そこで大丸有のビジネスエリアには、役割や立場、さらにはそれに伴う行動や責任から一時的に解放され、自然な感情を表現できる場所が必要なのではないかと考え、調査を進めました。ここで注目されたのが「Asyl(アジール)」という概念です。「避難所」を意味するアジールは、日々の役割や責任から離れ、自分の感情を自由に感じられる空間です。
大丸有エリアのようなビジネスエリアにも、心の休息や感情を表現できる場が求められているのではないかと考え、このエリアでアジールな空間を探求することが本プロジェクトの一つの目的となりました。

大丸有におけるアジールスポットの例1

大丸有におけるアジールスポットの例2
4.感情の避難所を探る旅:Emotional City Mapと体験型ツアーの成果
私たちのチームは、効率性が優先される大丸有エリアを舞台に、都市空間に潜む感情の避難所「アジール」を捉え、新たな価値を引き出す挑戦をスタートしました。
まず、アンケートを通じてエリア内で働く人々の感情の動きを探ることから始まり、オフィス街である大丸有の中でどのような場面でどのような感情が湧き起こるのかをヒアリングしました。その結果を基に、現地のフィールドワークで具体的な場所を歩き、感情がどのように空間と結びついているのかを観察しました。
「Emotional City Map」は感情価値指標を基に、空間を色分けして感情の動きを可視化した地図です。例えば、人目が気にならない緑地や無感情でいられるカフェ等、各場所が持つ感情的な特徴を示しています。地図にはアジールな空間の5つの要素を抽出し、それらをカラフルな葉として表現しました。また、大丸有エリアのアジールスポットは、色の濃さで表現された「オアシスの泉」のイメージで、色が濃いほど自然体でいられる場所であることを示しています。

Emotional City Map
また、大丸有エリアのアジール度という観点での現状や課題を把握するため、大丸有エリアと回答者の好きな街をアジール度の観点で比較してみました。アジールな空間で感じられる5つの要素を抽出し、それぞれの要素について、大丸有エリアと自身の好きな街でどの程度感じられるかを5段階で評価していただいたアンケート結果を平均化することで、回答者が理想とするアジール(好きな街の評価平均)と大丸有エリアの評価を比較して可視化しました。
その結果、大丸有エリアにおいては、自分の好きな街に比べて“アジール”を感じることが難しいという回答が多く見られました。この調査から、大丸有エリアが持つ独自の都市環境と、人々が「安心感」や「解放感」を感じられる空間づくりについての課題が浮き彫りになっています。

都市別アジールレベルの比較図
さらに、実際に大丸有のワーカーに、アジールの存在や大切さに気付いてもらい、都市における感情価値の重要性について考えるきっかけを作るため、大丸有エリアという感情の砂漠における感情の避難所をリアルに体験してもらうEmotional City Tourを実施しました。Emotional City Tour(タイトル:FINDING ASYL)は、参加者が大丸有エリアを歩きながらアジール(感情の避難所)を探す体験型のツアーです。
ツアーでは、参加者は仕事という責任から逃れるために、自分にとって心地よいアジール空間を見つけるミッションに挑みます。参加者はアジールの概念を理解し、自分の感情が自由に表現できる場所を見つけるプロセスを体験します。まず参加者はアジールスポットの例を写真で確認し、アジールに関する理解を深めました。

アジールに関する理解を深めるインプットの様子
次に参加者は、大丸有エリアのアジールスポットを探索し、自分なりにアジールだと思う場所を一つ見つけ、、その場で水を注ぐ儀式を行います。これは感情の砂漠にオアシスを生み出す象徴的な行為を示しています。最終的に、参加者は都市空間が持つ感情的価値をより深く理解し、自分にとってのアジールを見つけることができました。

感情の砂漠にオアシスを生み出すことの疑似体験の様子
5.「アジール」を都市に:オフィス街に隠れる特別な空間の魅力
都市のアジールに関する活動を通して、喜びや安心、時に悲しみを感じる場所など、都市空間がさまざまな感情価値を内包していることがわかりました。特に、大丸有エリア内での「アジール」な空間は、オフィスビルの間にある小さな緑地や、隠れたカフェの一角などに多く見られました。
感情価値の可視化により、日々の生活の中で無意識に感じている場所の価値が改めて浮き彫りになり、都市空間に新たな魅力を付与することが可能であると考えられます。
本活動を通して「アジール」という概念を知ってから、ふとした瞬間にその存在を意識することが増えました。たとえば、赤い色を意識していると街中で赤いポストや看板が目につくように、アジールを意識するようになると、歩いているだけでその特徴や匂いのようなものを自然と感じるようになりました。特に興味深いのは、アジールが往々にして人目につきにくい場所や、少し探検が必要な場所にあることです。入り組んだ小道の先や静かな隅っこ、そういった場所にたどり着くと、なぜか特別な価値を感じます。アクセスが容易で誰もが使えるように設計された空間が、必ずしも「自分にとってのアジール」にはならないのと同じように、アジールにはある種の個別性が求められるのだと実感しました。また、興味深いのは、個々の人が好むアジールの特徴から、その人が潜在的に求めている環境要素を読み取れる点です。自然が多い場所を好む人、人目を避けたい人、逆に活気ある場所で感情を表現したい人。それぞれが選ぶ場所には、その人の心の状態や深層的なニーズが反映されているように思います。このようにして考えると、アジールはただの「落ち着ける空間」ではなく、自分自身の内面を見つめる手がかりにもなります。街を歩く中で目に映る風景や、足を踏み入れた空間が自分にとってどのような意味を持つのか。日々の中で立ち止まって考えてみる価値があるのではないでしょうか。
6.感情価値×都市計画:City Life Experienceチームの役割とは
私が所属するCity Life Experienceチームでは、都市全体だけでなく、そこで生活する人々にも焦点を当てることを重視しています。特に本プログラムのような「感情」に注目する取り組みは、ユーザー理解を深める大きな鍵になると考えています。
これまでのように都市全体やユーザーを客観的に捉える視点に加え、人々の感情や深層心理にフォーカスしたボトムアップ型の視点を取り入れたまちづくりが、これからますます重要になると感じています。
今後は、感情価値を考慮したコンサルティングを通じて、ビジネスエリアで働く人々にも感情価値を提供し、都市の魅力を多面的に引き出す提案を行っていきたいと考えています。

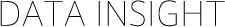



あわせて読みたい: