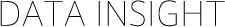はじめに
はじめまして。NTTデータの與嶋 清貴(よしま きよたか)と申します。
周りから「きよ」と呼ばれることが多いので、ぜひ「きよ」で覚えていただけると嬉しいです。
NTTデータに入社以来、飲食店や小売業の販促企画を経験したのち、組織異動を経て、まちづくり領域でのユーザー体験のデザイン(ユースケース創出)を担当し、現在は新規事業伴走を行うチームにてサービスデザイナーとして活動しています。「サービスデザイン」という言葉に聞き馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、事業/サービスをエンドユーザーの目線で考える存在として、ユーザー調査を通した課題/機会の明確化、それに対するアイディア創出、体験ストーリーの作成といった新規事業検討に深みを生むことに主軸を置いているメンバとして捉えていただければと思います。
新規事業の構想には顧客の課題から捉えるユーザー起点、経営資源・技術から考えるアセット起点、目指したい姿から定義していくビジョン起点などの状況に応じた様々なアプローチがあると思いますが、この場ではユーザー目線で検討を重ねる上で感じる難しさや向き合い方を新規事業、新規サービスを考えるみなさまと共有できればと思っています。
今回のテーマは私が業務に取り組む中で、検討者によって色濃く差が出ると感じる「ユーザー体験のデザイン」についてお話ししていきます。
なぜ新規事業でユーザー体験を描くのか?という意味について考えながら、個人的に意識したいポイントをまとめていますので、少しでも目を通してもらえると嬉しいです。
そもそもユーザー体験をなぜ描くのか?
デザインアプローチでユーザーを捉えユーザー体験を描くことに対して、代表的なアウトプットとしてはペルソナやカスタマージャーニーマップ(CJM)等があると思います。実際に作成をしたことがある方ならば、このアウトプットの有用性は何なのか?と何度も考えたことがあるかもしれません。
ユーザー体験を可視化することに対し、私は大きく3つの意味があると思っています。
(1)自分自身の目線をユーザーに近づけるため(当事者意識を醸成するためのジャーニー)
ユーザーの目線に立つという内容と逆接的な言い方になるかもしれませんが、自身がドンピシャのターゲットでない限り、ユーザーの行動、感情の変化を理解することは難しいと思います。だからこそユーザー調査(ヒアリング、インタビュー)を重ね、ユーザーの現状に入り込んで体験の流れを捉えることが、明確に視点を変える一歩であり、当事者としての熱量を生むことにつながると考えています。
(2)課題って何だ?提供価値による体験の変化って何だ?の解像度を高めるため
CJMを描くときはAs-IsとTo-Beでどう体験が変わるのかを意識し、As-Isでは課題を、To-Beでは提供価値を明確にしていく必要があります。何が課題で提供価値なのか、これらを箇条書きで並べてみるとシンプルだと思いますが、あえてジャーニーに組み込んで描くことではじめてユーザーのリアリティが生まれると思っています。そしてそのリアリティのあるシーン・状況を切り出すことで、その課題/価値の有無(本当にあるのか?)の見極め、仕組み/ソリューション(どう実現できるのか?)との接続方法が見えてくるのではと考えています。
(3)ユーザーへの共感(エンパシー)を生むため
デザインアプローチで作り上げるアイディアに魅力を持たせるためには、共感性を込めることが不可欠だと考えています。ここで言う共感とは、「確かにありそうだし大変そうだ」と思ってもらうことではなく、「その課題は何とかするべきだ、解決したい」と自分事レベルで思ってもらえることを指しています。つまり、シンパシー(感情に寄り添う)だけではなく、エンパシー(感情を自分事として感じる)を引き出すものを目指すことで、チームメンバ、関係者、そして何より事業主体者(自分自身)が想いを持って推進できるようになると考えています。
ユーザー体験を描くときの考え方4選(個人的に意識したいポイント)
これまでの経験から、体験を自身で描くとき意識しているポイントを4つあげています。
上手くいったことだけでなく失敗から学んだケースも多いですが、失敗から得る学びは強く残るため、大切なのはチャレンジの連続だと改めて実感しています。
(1)まず描く、まず作る、まず可視化する
まずはユーザーの動きをどんな形でも可視化すること、そうすることで対話が進み、体験を磨いていく土台として機能すると考えています。ユーザー起点の意見交換は個人の主観での空中戦になりがちのため、よく何の時間だったのか?と思うこともありますが、土台を用意するだけで、ただの主観的な意見ではなく共感を持った点に関する発言につながりやすくなり、課題/価値が何か?を探る分析が進み始めると思います。「百聞は一見に如かず」という言葉がありますが、それと同様に「十考は一作に如かず」(勝手な造語です)と言えるのではと思うほど、まず手を動かして可視化してみることは効果的だと思っています。
(2)情報の粒度にこだわる(頭の中でイメージできるか問い続ける)
ユーザー体験を実際に描く中、検討フェーズに応じてアウトプットの内容は異なると思います。(初期のアイディアスケッチであれば端的にイメージを伝える、ストーリーボードであれば具体的なシナリオ作成、CJMであれば流れのある各シーンにフォーカスできるように行動・感情を描く等)
特に体験をより詳細に分析的に捉えていくCJMでは、「ユーザーがどう動き何をしているかを頭の中でイメージできるか」を問い続けることで、「知った気になっていたが実はわかっていないこと」、「ユーザーが本当に嬉しいのかという違和感」に気づくことができます。
(3)体験は一通りではなく複数あることを意識する
To-Beのユーザー体験を描いたとき、当たり前ですがそれはあくまで目指したい理想の体験です。ユーザーはそれ通りにシーンを踏んでくれると限らない中で、一通りしか体験を意識しないのは価値の幅出しにつながらずもったいないと思っています。出発点は一緒でもそこからの分岐を考えてみる、あるいは全く別の入口からの体験の流れを作って比較してみることで、思いもよらない課題に気づくことや、絶対に外せないコアとなる体験が見出せることがあると思っています。
(4)体験の前後を含めて想像する
ユーザーを捉えるとき、本当にユーザー=生活者の目線になれているか?ということを常に問うことが必要だと思っています。私が過去に美大の社会人向け履修プログラムに通っていたとき、“ナラティブ”という考え方に出会い、ユーザーとサービスの関わりを物語的に現在進行形で捉えることで、利用・経験する中でサービスを使う意味をもってもらえるかという目線が重要だと学びました。
事業/サービス検討でユーザー体験を描くときには、主に課題/価値を感じる一連の流れを切り出して表現することが多いと思いますが、その前後にはどのような生活があり、このサービス・体験を得ることが何につながるのかを意識して描くと、事業/サービスで実現したいことの解像度が高まるのではと思っています。
「ユーザー体験のデザイン」というテーマでここまでお話ししましたが、考え方によって描き方が大きく変わると思いますし、実際のユーザーを想定しているからこそ事業の質が変わる可能性を秘めているポイントだと感じています。
今回の話を通して、新規事業を考えるみなさまの中で共感できる点、整理のきっかけになった点があれば嬉しいですし、新たな気づきや考え方の変化につながっていればより一層嬉しく思います。