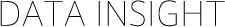豊かに人を成長させるインターフェイス
ーー研究室のテーマについて教えていただけますか。
研究グループの「Fluid Interfaces」では、ウェアラブルデバイスなどを中心に、今日の私たちの生活とデバイスとの関係軸をよりシームレスにしていくことを目指しています。現在は誰もがスマートフォンを持ち、PCやタブレット、スマートウォッチといったデバイスと生活していますね。その影響は計り知れません。ときにはPCの使いすぎで首や腰を痛めたり、睡眠の質を下げたりすることもあり、個々人のメンタルヘルスやコミュニケーションにも影響があります。2人で同じ席に座っていてもずっとスマホを見てしまいがちになるなど、デバイスがひとつ机上にあるだけで心理状況は変わりますよね。そうした数多の負の影響も免れない現在のデバイス環境において、私たちはより人々の生活が豊かになるように設計されたシームレスなインターフェイスをつくることで、こうした状況に働きかけることを目標としています。
――そのインターフェイスとはどんなものでしょうか。
スマホやスマートウォッチなどのインターフェース・デザインは、いかに情報を届けるかにフォーカスされています。そこでは、やる気や集中力、クリエイティビティといった人々の健やかな暮らしに必要な要素のクオリティにはあまり注力されていません。しかし、いまや一日24時間デバイスと共に過ごす時代において、それらがストレスを軽減したり、悪い習慣を変えたり、記憶やクリエイティビティ、注意力の拡張なども助けるような重要な役割を占めるようになってくるでしょう。私たちは研究グループを「Fluid Interfaces」と名付けましたが、これは個々人がなりたい自分になることをサポートするための、シームレスでなめらかなパーソナルデバイスにおけるネクストステージだと考えています。
――具体的にはどんなものが考えられますか?
現在のデバイスは普段から常に注意を向けるように求めてくるため、いま外で実際に起きていることから私たちを切り離してしまいます。でも今後は、逆に私たちの知覚を拡張することで、実世界とデバイスの世界をより良くつなぎ、デバイスへのタスクを減らしてくれるようになるでしょう。たとえば我々が開発したメガネにはAR機能が付いていて、私たちの視覚認識を拡げてくれます。また、聴覚の補強も興味深いです。最近はノイズキャンセリングのヘッドフォンも増えていますが、さらに周囲のノイズを下げることで会話に集中できるようになるでしょうし、自身の声量を増幅してくれたらどうでしょう?ただノイズをブロックするだけではなく、より聞きたいことへの注意が自然と向くようになるのです。
ほかに最近では、”自問自答”を助けてくれるシステムの研究を進めています。もしあなたが自問するように何か問いかけたとき、大声で話しかけずともそのシステムがGoogleから検索して答えにアクセスできるような情報をあなたの耳に囁いてくれる。そんなシステムです。それをいかに自然なかたちで、かつ混乱なく実装できるかが重要だと考えています。
自分だけの“センセイ”が生活に寄り添う
――機械は話者の感情やコンテキストを理解し、自発的な対話能力を獲得しつつあります。人に新たな気付きを与え、人の思考を支援する存在となる日も近いでしょう。
AIにまつわる様々な議論の中で、AIに敵対する傾向や人々を脅かす存在としてみなされることが多々ありますが、AIは我々を補完してくれる素晴らしいポテンシャルを秘めていると私は思います。人々とAIが互いに補完し合い、深く助け合うことで、これまでの能力をしのぐようになるでしょう。身体上か認識上かに問わず、その拡張は今後ホットなトピックになっていくと私は思います。また、AIが私たちの身体またはメンタルを拡張するようデザインされたツールになりうると考えられています。
もちろん、すでに現在の私たちはテクノロジーによって強化されていますが、その方向はAIシステムの発展と展開によって今後もさらに良い方向へと進むでしょう。もう一方で、スマートテクノロジーを通して、人が他者と学び合うような方向も促進したいと思っています。
「Be My Eyes」という視覚障害者向けのサービスでは、他者の助けを借りながらも、自立して生活できるようにサポートしています。たとえば、視覚障害の方が料理をしている時にオーブンの写真を撮ってサーバーにアップロードすると、そのときにログインしている他のユーザーその写真にリプライして「200℃に設定されているよ」と教えてくれる。そうした、リアルタイムな他者によるサポートも賢いテクノロジーによる拡張の一種だと考えています。
――「Wearable Wisdom(ウェアラブルな知恵)」という研究テーマもそれに近いものでしょうか。
はい、日本語で Teacherは「センセイ」でしたよね。それがメガネの中などにいて、生活にすっと溶け込んでいたらどうでしょう?常に小さいセンセイが一緒にいて、あなたの考えや問いに対してアドバイスしてくれるようなイメージです。そのセンセイは知恵をその時々で授けてくれるあなたのおばあさんかもしれないし、いま直面する課題に対して適切なインプットを与えてくれるエキスパートかもしれません。けれど、そうした学習機会をリアルタイムで仲介してくれる完璧なシステムはまだ完成していません。これはWorld Wide Webの登場する前から私も長らく取り組んできたアイデアです。
――そうしたシステムは教育にも役立つのではないでしょうか。
そうだと思います。「学校」というシステムが誕生してから久しいですが、「学び」は学校がすべてではありませんよね。それに学校で学んだものは、すぐに忘れてしまいがちです。けれど、実生活の中で何かを発見し、もっと知りたいと思ったとき、そこにさらなる知識を教えてくれるメンターがすぐに現れたらどうでしょう?たとえば、木に石を投げて遊んでいるとき、石の重力や加速度、投げた経路などが可視化されれば、物理やニュートン物理学に興味を持つきっかけになるかもしれません。私たちの世界の不思議に興味を持ったとき、その興味をより深く学びへと促進してくれるようなシステムが必要だと思うんです。

メイズ教授の研究室
人の内側からサポートするデジタル治療
――Fluid Interfacesのヘルスケア分野への応用についてはいかがでしょうか?
ヘルスケア分野には、いま新たなウェアラブルデバイスがどんどん導入されるという機会に恵まれていますね。これまでのヘルスケアのウェアラブルは主に心拍数や呼吸、活動などのデータを収集することにフォーカスされていますが、実際の治療や健康維持についてはまだあまり活用されていません。以前開発したメガネには、眼球の運動や眼電図などから脳波の活動を測定できるセンサーを取り付けました。このセンサーから、その人が注意を払っているのか、気が散っているのかなどを判断できます。その分析はADHDやADD(注意欠陥・多動性障害)などの方にも効果的ですが、この刺激の多い現代社会で生きる人なら誰にでも使えるものだと思います。
たとえば、会議中に退屈で注意散漫になったとき、音や振動などのフィードバックを与えることで、人に知られず注意を取り戻すことができるでしょう。そうしたささやかなフィードバックが連続的に行われることで、自身の状況をより深くコントロールできるようになります。
これらのデバイスは常にその人の状況を記録しますから、たとえば精神面で不安を抱える人でも、いつ不安になるかがわかり、そのときどんなタイミングで深呼吸をすればいいか、または聞いている音楽の適切なボリュームや、心地良いリズムのパターンなどを教えてくれます。これらは人々の隣にいつも寄り添い、助けてくれるような存在になることでしょう。
――NTTデータと共同で行っている研究プロジェクト「Digital Memory Book(※)」は認知症、アルツハイマーの患者に向けた実践ですよね。
認知症患者への療法で、過去の写真やビデオなど見ることで、記憶を活性化していくことで知られる「回想法」というものがあります。外部のデバイスに過去の記録をタグ付けして構造化し、繰り返し患者に見せることによって、個々の記憶が場所や出来事、友人や家族などと紐付けられ、記憶が維持されやすくなるように設計されたデジタル回想の療法です。
こうしたデジタルによる回想方法は、疾患の進行を調べるのにも有効です。また治療だけでなく、過去の記憶を失うことで孤独を感じてしまう人々に対するメンタル面からのサポートにもなります。たとえば、ある訪問者の名前をすぐに思い出せないときでも、外部記憶にアクセスできれば、不安にならずに自信を取り戻せるようになるでしょう。再びその訪問者が現れても、ゲームのように記憶を思い出せるトレーニングを事前にしておけば、状態が悪化するのを防ぐことができます。
NTTデータでは、高齢化社会の大きな課題となっている認知症・アルツハイマーを課題として、現在、慢性疾患や予防的ヘルスケアの対応策として有望視されるソフトウェア、ITデバイスを用いたデジタル治療法(Digital Therapeutics)の研究プロジェクトを共同で実施中。Fluid Interfacesでこれまで行われてきた認知拡張の研究をベースに、認知症の非薬物療法としてすでに実績のある「回想法」を簡易に実施できるデバイス・アプリ(デジタルメモリブック)のプロトタイプを試作。認知症患者自身のメモリ補完とそれによる自尊心の回復、日常生活のサポートのみならず、その患者の介護者・家族の負担の軽減も目論む。将来的には認知症向けのデジタル治療薬として、病院、介護施設、家庭などへの展開を期待している。
「便利さ」よりも「能力を拡張する」テクノロジーを
――こうしたデバイスが生活に寄り添うようになる一方で、新しい技術への倫理観についてはどう思われますか?
私たちが目指すのは、人間の能力拡張と、人間と機械の統合です。そのビジョンは大きく描いていますが、一方で開発した技術の社会的、または人間的影響についても深く考察するようにしています。特にウェアラブルデバイスから得られるデータは、とてもパーソナルな情報です。こうした個人的なデータを取得する際、完全に非公開で、個々人の管理下でコントロールできるのか、またそのデバイスを使う人々が技術のシステムや、その限界点が何かをしっかり理解できているかも重要です。
私たちは常に、ユーザーのほうに知識と選択肢があるべきだと考えています。大企業や政府などからの要請で使うのではなく、ある技術にどんな価値や効果があるのか、それらがどんな仕組みにあるのか、理解した上で選択できることが重要です。
――使う側のリテラシーも求められるんですね。
ええ、テクノロジーに依存しすぎないことも重要な課題ですね。ある特定のタスクを機械に任せ始めると、自分たちでほとんどできなくなってきてしまいます。子どもが5歳くらいからスマホを持ちはじめ、最初からすべての計算を電卓でしていたらどうなるでしょうか。おそらく、数字や算術というものへの内面的な理解力が下がっていくでしょう。重要なのは彼らの計算能力が低下するかどうかではなく、理解力の欠如や、推論能力または思考力に影響を及ぼす可能性があることです。
つまり、これからはどの種のタスクを機械に託し、たとえ時間と労力が必要でもどの部分は人が自身で習得すべきスキルなのかを慎重に考慮する必要があります。しかし私は、そうした人のタスクを自動化するだけでなく、人が何かを学び、内在的な能力や知識を身につけることに機械が役立つことを期待しています。

メイズ教授が手に持つウェアラブルデバイスは、胸元につけて使用する。使用者の気分を平常に戻すような匂いを発する。
多様な問いから生まれる気付き
――どの研究も実社会への応用が鍵になると思います。産学連携についてはどう考えていますか?
その点で言うと、MITメディアラボの独自性は企業、研究者の両者にとって、互いに有利なかたちの産学連携を発明したところにあると思います。私たちは常に企業と密接にコラボレーションしていますが、企業から指示を受けているわけではありません。それでも、彼らが接する現実社会から見えてくる視点は私たちの研究にとって非常に貴重ですし、いま起きている問題に注力できます。
企業の側は、研究への投資が最終的に製品やサービスへつながることを目指しますから、実社会への応用はより早くなる。そうして研究を実社会に実装してみると、また新たな課題が見えてきます。そうした試行錯誤から、より本質的な課題に取り組んでいきたいと思っています。
——メディアラボでは学際的な交流も活発ですね。
最高のイノベーションは、多様なチームから生まれると信じています。そのため、私たちの研究グループは、AIの研究者をはじめ、電気工学のエンジニア、神経科学者、心理学者、そしてデザイナーなど幅広いバックグラウンドを持つ人々で構成しました。また、アート&サイエンスのアプローチも非常に重要だと思っています。優秀なアーティストのなかには、世界がどこへ向かうべきかを問い、また私たちが意識すべき問いに気づかせてくれる人もいます。「問い」を生み出すのがアートであり、デザインは私たちの研究を、より多くの人々に関わってもらえる形へと変換してくれます。あるジャンルや属性に偏らず、性差や人種も越えて議論できる場をつくる。こうしたアプローチから新しい発想が生まれ、良い仕事へとつながっていくんです。
——学際性以外に、ジェンダーバランスなどにも配慮されているのでしょうか。
ええ、メディアラボには専属のコーディネーターがいて、女性の活動を支援し、働く中で生じる様々な問題をサポートしてくれています。また男女問わず、卒業後のキャリア支援やポートフォリオの作成のメンターなども行っています。最初の専属コーディネーターは女性で、彼女の働きによってかなり大きな変化がありました。現在、メディアラボにやってくる学生や研究者の男女比は、5:5になりましたが、そこに至るまでに彼女のような存在は必須だったと思います。
――すばらしいですね。最後に、「Fluid Interface」の将来的なビジョンについて教えてください。
人々の可能性を最大限に発揮できる未来ですね。テクノロジーは個々の生活から消えることはこの先ないでしょうが、今後はより健康的な生活を送るのを助け、学び、成長する機会を提供してくれることで、私たちの人生を最大限に活かす支援をしてくれる存在になるでしょう。そのとき個々人のレベルや能力に合わせてサポートしていく技術がより一層求められます。そのとき、現状のスマホやPCなどのように、常にスクリーンを眺め続け、現実の生活から引き離してしまうようなものではなく、もっと自然と私たちの実生活になじみ、また人々がそれぞれなりたい自分へと成長する助けになるインターフェイスを開発していきたいと思っています。

取材・文:塚田有那 撮影:野口正博