- 目次
現代のサプライチェーンを取り巻く環境
近年、自然災害や地政学リスク、経済安保政策の影響を受け、サプライチェーンにおける需要と供給の変動や不確実性が高まる中、SCMでは強靭性や持続可能性といったレジリエンス強化が求められています。
時代の変化に伴い外部環境があまり変化しない、将来が予測できる前提の“静的サプライチェーン”から、供給に影響を与える要因が多様化し、ボトルネックが調達、生産、物流と様々な領域で発生する変動、不確実性を前提とする“動的サプライチェーン”へのマネジメントが求められるようになっています。
動的サプライチェーンの実現に向けて
では、動的サプライチェーンの実現に向けて、どのようなことが求められているのでしょうか。サプライチェーンの不確実性(≒強靭性)や気候変動問題(≒持続可能性)への関心の高まりを受け、“レジリエンス強化”と“GHG(温室効果ガス)排出量管理”への取り組みが各企業で注目されています。
まず、レジリエンス強化の事例をご紹介します。ある電気メーカー様では、会社間で生産や在庫、出荷情報の共有が適切にできておらず、過剰在庫や在庫欠品が多い状況にありました。更に、部品の需給調整の頻度が高いことが課題でした。そこで、4工場と100を超えるサプライヤーに対して企業間の需給情報を管理するプラットフォームを構築しました。
生産計画、発注、納入、在庫情報を一元管理し、アプリケーション上のグラフと表を原本とすることで、煩雑なExcel管理が不要となりました。その結果、当初計画した在庫の最適化に加え、報告資料の作成負担が軽減し、さらに問題発生の検知、影響確認が迅速になったため、先手の対応が可能となりました。
次にGHG排出量管理の事例をご紹介します。ある化学メーカー様は、世界的な原料高騰や急激な円安などを踏まえ、製造拠点の業務評価について収益性評価にGHG観点の評価を加えた収益性とサステナビリティの両輪経営を目指しました。具体的には、環境負荷を含むESGのパフォーマンスデータを一元化し、IR情報開示を行いました。環境データへのアクセシビリティを高めることで、社内の意識変革やサプライヤーマネジメント業務の効率化を実現しました。
NTTデータが目指すDigital Twin Supply Chain
当社の目指すDigital Twin Supply Chainは、“リアルタイムに可視化されたデジタルサプライチェーンを活用し、迅速で高度な経営判断を実現すること”と定義しています。

図1:NTTデータが目指すDigital Twin Supply Chain
企業にとって、Digital Supply ChainやTwin Platformを用いた動的サプライチェーンの実現は必須ですが、日本ではその前段階にあたるIoTやAI、MLなどデータ利活用も現在道半ばという状況にあります。動的サプライチェーンはあらゆるデータの統合により実現されるため、まずは短期的には局所で業務の改善を進めながら、段階的にデータを収集・蓄積していく必要があります。
グローバルサプライチェーンにおけるデータ統合基盤の導入事例
グローバルサプライチェーンにおけるデータ統合基盤の導入事例をご紹介します。
A社では各国で個別のERPを導入していたため、受注や在庫計上のオペレーションが国別で異なっており、またExcelやメール、電話を用いた“力ずく”の需給調整が負担となっていました。さらに、各国でマスタやコード体系が異なるため、各国横断での販売、在庫の集計は膨大な手作業となっていました。
これらの課題を解決し、グローバル在庫の可視化と需給計画標準化を実現するために、下図に示す各ポイントの通り業務改革とITの整備を両建てで推進しました。

図2:グローバルサプライチェーンデータ統合基盤実現のポイント
(1)需給業務標準化
販売、購買、生産の計画は統一のグローバルコードと標準化されたワークフローにもとづいて「計画立案→計画、実績対比→計画修正」のサイクル運用の標準化を実現しました。各国の集計方法やKPIの算出方法を同じ基準で定めます。実績値のみではなく、計画との乖離やその原因を追究する事で計画値の精度向上を促すサイクルを作ります。現場メンバーを巻き込むことで、グローバル需給計画実績データにもとづくPDCAサイクルの確立を実現しました。
(2)オペレーション標準化
一貫した視点でデータを可視化するには、データの源流となる業務の整備が必要です。例えば、積送中の洋上在庫の管理方法や、在庫のステータスや廃棄ルール、生産指示や取り消しのルールといった、等、キーとなる業務を揃えて標準化することで源流からデータ品質を向上しました。
(3)システム基盤
各国SAP/ERPからデータを収集、変換し、各国ローカルコードをグローバルコードへマッピングして、拠点横串での可視化を可能にするデータ統合と可視化基盤を構築、提供しました。KPIはグローバル統一で定め、同じ基準で計算した結果を1つのダッシュボードとして横並びで可視化しました。ExcelやCSVなどでも取れるデータを全て一か所に集め可視化し、ダッシュボードとして見せる事でデータの精度向上をはかりました。
(4)グローバルコード・マスタ整備
グローバルの販売状況を一貫した視点で分析するため製品と顧客のグローバルコードおよびグローバル属性を定義し、横串での情報分析を可能にしました。グローバルマスタはいかにメンテナンスをしていくかというのが重要です。まず、拠点ごとにマスタ情報最新化の責任者を指名し、次にグローバル属性付与に関する各国共通のルールを整備します。そして、更新が必要なデータ項目はシステムで日々アラームを上げる仕組みを構築し、更新漏れや遅れを防止します。これによりグローバルでの販売、生産状況を日次で把握し、アクションを打てる仕組みの構築が可能です。
(5)KPIレポート・ダッシュボード
情報基盤上で、グローバルでの販売、在庫、PSIの可視化のために重要KPIを定義しました。全体を俯瞰できるダッシュボードと、詳細分析が可能な集計明細レポート群を提供することで、各レイヤーが同じ数値を見て会話する事が可能になります。また、ダッシュボードの活用により、個人による手作業でのデータ集計が不要となり、生産活動に充てることが可能です。
(6)グローバル採算性簡易分析
販売情報と製品別標準原価により顧客、地域、製品別にグローバルでの利益(粗利)の簡易分析を実施しました。グローバル製品マスタで各品目がマッピングされたことにより、連結ベースの顧客別、製品別の粗利を日次で把握できるようになりました。また、年次予算、月次計画についても、先々の採算性(着地見込み)を見ながら施策を考えられる業務プロセスとITを整備する事により、より精度の高い予算の策定や実績を踏まえた着地見込みの算出が可能となりました。
まとめ
製造業のグローバルSCMにおいて、地域、部門、拠点ごとの情報の分断がコミュニケーションのコストやスピードへもたらす影響が課題の根幹にあると考えています。
データ基盤を整備、活用し、業務標準化やコード統合、KPIマネジメント等の改革により、より俊敏かつ柔軟なグローバルSCMの実現が可能です。その結果、データドリブンの在庫最適化、プロセス品質向上、利益ベースのマネジメントが可能になります。
これにより、企業は変動する市場状況に柔軟に対応でき、適切な意思決定が迅速かつ正確に行えるようになります。データドリブンなアプローチは、製造業における競争力の向上と持続可能な成長を支える重要な要素です。

図3:グローバルSCMにおける課題
当社はこのような製造業への実績をもとにTableauにてサンプルダッシュボードを用意しております。実際の業務の流れに沿ったダッシュボードの操作を実演することも可能です。

図4:Tableauのサンプルダッシュボード例

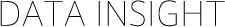



Tableau(タブロー)についてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/tableau/
製造業におけるデータ活用の最前線~ステップ別アプローチと活用ユースケース~についてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/event/archive/2024/129/