- 目次
1.IOWNの技術を簡単に理解する
IOWNの技術を簡潔に説明すると、光の技術を軸とした次世代の通信・コンピューティングインフラです。従来の電気信号を光に置き換えることで、低消費電力、大容量、低遅延を可能にします。
図1のイメージのように電気回路を光装置に置き換えることで、電気と光の変換によるロスや遅延を抑えられます。さらに、光は電気よりも省電力で高速に伝送できる特性もあるため、ネットワークの端から端まで光でつなぐことで、その利点を最大限に引き出すことができます。

図1:電気から光への置き換えイメージ(引用元:NTT技術ジャーナル)
2.IOWNの利点とは?
IOWNには、現代の社会課題を解決するための多くの利点があります。ここでは、省電力化による環境負荷の低減や、大容量・低遅延の通信がもたらす新たな可能性について紹介します。
2-1.省電力:生成AIの電力消費を削減
生成AIの普及により、データセンターの需要が急速に増加しています。それに伴い消費電力の問題が顕在化しています。
IOWNのコンピューティングインフラを使用することで、2026年頃には消費電力を現行の1/8に削減し、将来的には2032年頃には消費電力を1/100にめざします。
この低消費電力を実現する技術については、第3章で解説します。

図2:低消費電力の実現(引用元:インダストリーAIクラウドによる社会課題の解決)
2-2.大容量、低遅延:大量データのリアルタイム処理を容易に
IOWNでは、マルチコアファイバなどの新しい光ファイバによる大容量光伝送システムや、情報を圧縮せずに伝送する技術など、多くの新技術を導入しています。これにより伝送容量は125倍、遅延は1/200を目標としています。

図3:IOWNの利点(引用元:IOWN オールフォトニクス・ネットワークとはなにか)
大容量、低遅延のインフラが提供されることで、さまざまなユースケースが可能となり、社会の変革を促します。例えば、モビリティ分野では、車、人、環境の状況をリアルタイムでモニタリングし、AI処理とフィードバックを行うことで、安全かつ自由な移動を実現します。
3.IOWNを構成する3つの主要技術
IOWNの革新性を支える3つの中核技術「APN」「PEC」「DCI」の概要と、それぞれが果たす役割を紹介します。
3-1.APN(オールフォトニクス・ネットワーク)
APNは、上記の図1のように端末からネットワークのすべてに光(フォトニクス)ベースの技術を導入することで、圧倒的な低消費電力、高速大容量、低遅延の伝送を実現します。
APNは既に実用化されており、2023年3月からNTT東日本、西日本がAPN IOWN1.0の商用サービスを開始しています。光信号を電気信号へ変換することなく光波長のまま伝送し、従来のサービスに比べて1/200の低遅延を実現しています。
さらに、APNでは遅延の揺らぎがなくなるメリットもあります。従来のTCP/IPベースのネットワークでは、状況によって遅延が大きく変動するため、リアルタイム性が求められるサービスにおいて課題となっていました。APNでは遅延が一定となり、予測が可能になります。これにより、遠隔地での複雑な作業や高精度のリアルタイムデータ通信が容易になります。
次のステップとして、2024年12月よりAPNサービス「All-Photonics Connect」を提供開始しています。このサービスではユーザー拠点間としては世界最高水準の最大800Gbps(帯域保証)の高速大容量通信を提供します。

図4:APNサービスの拡充(引用元:電気通信市場検証会議資料)
3-2.PEC(光電融合)
PEC(光電融合)は、これまで電気で処理していた領域を光に置き換えていく技術です。
電力と比較すると光には消費電力において大きなメリットがあります。電気配線では高速化(周波数増加)や伝送距離延伸により消費電力が大幅に増加しますが、光では消費電力はほとんど増加しません。

図5:光の低消費電力性(引用元:IOWN 機能と特性)
PECは技術の適用領域により4つの世代を規定しています。
PEC-1はネットワーク領域でデータセンター間を光化します。こちらは既にAPNで商用化済みです。PEC-2ではコンピューティング領域に入ってボード間を光化します。PEC-3ではボードの中にあるチップ間を光化します。PEC-4ではチップの中まで光化する計画となっています。

図6:光電融合技術の世代と適用領域(引用元:電気通信市場検証会議資料)
3-3.DCI(データセントリックインフラストラクチャ)
DCIは、IOWN2.0以降においてPEC(光電融合)をコンピューティングの領域に適用した新しいデータ処理基盤です。CPUやメモリ、GPUなどのリソースを細分化し、必要なものだけを稼働させることで高効率化と低消費電力化を実現します。
従来の電気配線では接続距離に制限がありましたが、光配線を使用することでリソースへの接続距離が延長され、仮想的に大規模システムでのリソース最適化が可能になります。さらに、APNによって地理的に分散した複数のデータセンター間にも適用されれば、巨大なスケールで高性能かつ電力効率の高いICTインフラを実現できます。

図7:DCIのリソース利用イメージ(引用元:電気通信市場検証会議資料)
4.IOWNロードマップ
IOWNはネットワークからコンピューティングまでPEC技術を軸に段階的に実装されます。
IOWN1.0ではデータセンター間をAPNで接続する商用サービスが既に展開されています。次にIOWN2.0ではコンピューティングの領域をカバーし、2026年頃にDCIを実装したサービス展開が予定されています。さらに2028年以降には光電融合デバイスの進化(チップ間、チップ内配線の光化)、APNの伝送効率向上、DCIのアーキテクチャの進化などによりIOWNの高い最終性能目標(図3参照)の達成をめざしています。

図8:IOWNロードマップ(引用元:NTT R&D FORUM 2024講演)
5.IOWNの活用例
IOWNの技術は社会のさまざまな分野での問題解決に役立ちます。ここではNTT DATAでの取り組みを中心に活用例を紹介します。
5-1.遠距離データセンター間接続
分散型データセンター実現に向け、イギリス、アメリカの各国でデータセンター間のAPN接続に関する実証実験を行い、約100km離れた拠点間を1ミリ秒以下の低遅延で接続することに成功しています。都市部と郊外のデータセンターをAPNで接続することで、あたかもひとつのデータセンターであるかのように扱える統合ITインフラの構築が可能となります。これによりリアルタイムAI分析など低遅延性が求められるユースケースや信頼性と耐障害性が求められる金融分野での活用が見込めます。
5-2.離れた拠点からのロボットの遠隔操作
工場設備を対象としたスマートメンテナンスの実現に向け、遠隔操作型ロボットによるリアルタイムの映像送信とAI解析の検証を行っています。
6.さいごに ~IOWNで実現する未来の社会基盤~
この記事ではIOWNを構成する主要な3つの技術とその活用例を紹介しました。 IOWNが通信とコンピューティングのインフラとして実装されると、大量かつ多様なデータを低コストでリアルタイムに処理できるようになります。これにより、デジタルツインコンピューティングなどの先進的な社会基盤システムやアプリケーションが構想され、広範な分野での問題解決と新たな価値創造が期待されています。
参照:IOWN構想特集 -デジタルツイン コンピューティング-
NTT DATAでは2030年代にこれらの技術が当たり前になる未来を見据え、いち早く社会に貢献できる基盤の実現をめざして取り組んでいます。

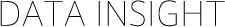



IOWN構想とは?についてはこちら:
https://group.ntt/jp/group/iown/
NTT IOWN Technology Report 2024についてはこちら:
https://www.rd.ntt/research/RDNTT20241031.html