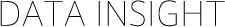- 目次
1.いま、世界で活況な業際ビジネス
業種業界を越えて協力し、ユーザーを巻き込んだ新しい価値を提供する「業際ビジネス」が注目されている。例えば、世界最大規模の小売業「ウォルマート」の取り組む「インホーム デリバリー」というサービスが分かりやすいだろう。
このサービスは、注文した商品の配達サービスだ。興味深いのは、商品をただ配達するのではなく、留守の場合でも配達員がスマートキーで宅内に入り、商品を冷蔵庫に収めることだ。その様子は、配達員が装着したウェアラブルカメラで中継され、利用者のスマートフォンで確認できる。確かに配達サービスは便利だが、生鮮食料品の取り扱いには課題があった。冷蔵庫に入れてくれたら便利だが、留守中に家に入られるのは心配。そんな生活者の率直な感覚を、ITが解決している。まさに、小売業と運送業をITで融合した業際ビジネスと言える。
業際ビジネスが重要視される背景には、テクノロジーカンパニーによるデジタルディスラプションがある。特に、GAFAを始めとした巨大IT企業の勢いはすさまじい。医療、AI、次世代家電、自動運転、Fintech、スマートシティなど、日本経済再生本部が発表した「未来投資戦略2018」で掲げられた重点戦略20分野のうち、既に8割に何かしらの形で参入済み、または参入予定とされている。
一方、日本企業の取り組みは遅々として進んでいない。水平統合型のGAFAと比べ、未だ7割の企業が垂直統合型で、小売りなら小売りのみ、製造なら製造のみと画一的なサービス提供に留まっている。
もちろん、この状況に危機感を覚えている企業も存在し、国内でも積極的な異業種連携が加速化しつつある。
グローバル競争に勝ち残るため、業際ビジネスで新しい価値を生み出すために必要な要素はなにか。私は、「テクノロジーの理解」、「生活者起点のサービス再構築化」、「業際域へのサービスシフトとコラボレーション」、「モノ、データ、処理など多角的な価値提供」の4要素だと考えている。
デジタルテクノロジーの進歩で業界の壁は壊れ、生活者体験の変革を起点に競争が激化している。ここでは、データ、モノ、処理など、多角的な価値提供が必要となる。そのためには、生活者起点でサービスの再構築を遂げ、生活者から選ばれつづけるしかない。
2.NTTデータが取り組む「MaaS」での業際ビジネス
NTTデータが業際ビジネスに取り込む理由。それは、さまざまな業界のお客様のビジネス変革をITの力で支え、社会基盤を構築してきた実績がある。だからこそ、それぞれの業界の結節点として機能し、お客様との新たなビジネスを協創できると考えているからだ。

図1:新たなビジネスの協創
業際ビジネスの推進には、生活者に寄り添うこと、すなわち生活者視点が重要だ。マーケットの動向や生活者、技術、データやパートナー企業、競合テクノロジートレンドなどから、自分たちの置かれた現在位置を確かめつつ、生活者起点で課題の解決策やビジネスアイデアを発見する必要がある。
とくに、今後生活者の体験が大きく変わる領域は手を付けやすい分野といえるだろう。NTTデータは、食と生活と健康を一連で捉える「Food&Wellness」、IoTによって都市生活そのものが変わる「Smart City」、そして、移動と消費体験がセットになった「MaaS(Mobility as a Service)」などで、お客様とのビジネス創出やPoC(実証実験)に取り組んでいる。今回は、そのなかでも「MaaS」について説明したい。
現在のモビリティ領域では、移動手段と目的地で提供されるサービスは連動していない。例えば、外食に行く場合、まずは行きたいレストランを調べて予約サイトで席を確保する。その後、予約日時にレストランへ到着するための移動経路や手段は、別のサービスで調べる必要があった。
自動運転が実現した未来ではこれらが統合され、移動中に目的地の情報やサービスがシームレスに提供・連携されるようになるだろう。移動するユーザーへのサービス提供ビジネスの市場規模は、数兆円という試算もある。
しかしNTTデータでは、将来的な自動運転向けではなく、今の交通手段や自動車からサービス提供を始めることが重要だと考える。そこで、移動サービスと目的地サービスを掛け合わせた新しい価値を「モビリティコマース」と称して、MaaS領域に取り組んでいる事業者との協創を進めている。以下は、その一例だ。

図2:モビリティコマースサービスコンセプト
モビリティコマースサービスは、車内に設置したデバイスにキャラクターが表示され、目的地周辺の観光情報やオススメ情報を表示するサービスである。個人に合わせてリコメンドを行い、お出かけをより便利にしていく。さらに、同乗者同士で予定を共有したり、ゲームや音楽などのエンタメを楽しんだりすることで、よりお出かけを楽しくしてくれる。現在は、提携しているデザインファームやゲーム会社とともにプロトタイプを作成中。モビリティ事業者や観光事業者と共に実証実験を進めており、事業化も視野に入れている。
NTTデータは、上記のような「生活者起点のサービス再構築」のために、業際ビジネスの推進を行っている。そのために、業際ビジネスに必要な4要素からなるケイパビリティ「DDBT」を設定した。

図3:DDBT概念図
『DDBT』は、「Design」「Data」「Business」「Technology」の頭文字。すなわち、「デザインとデータを起点としたテクノロジーによるビジネス変革」だ。異業種連携により新たな付加価値提供が求められるマーケットには、欠かせないケイパビリティである。
業際ビジネスにおけるデザインやデータ、テクノロジーの活用には、その前段となる「プロセス」と「人・組織」が重要だ。そこで、この2点において解説を行う。

図4:業際ビジネス推進のポイント
3.『DDBT』を活用するために必要な「プロセス」と「人・組織」
まずプロセス面だ。業際ビジネスでは、まだ誰も見たことがない新しいビジネスやサービスを考える。可能性を狭めず、探索的にさまざまな要素を検討し、試行錯誤を通して発見を積み重ねるプロセスが欠かせない。そして、その試行錯誤は、超高速で走りながら考える必要がある。
「超高速で走りながら考える」とは、『DDBT』、「Design」「Data」「Business」「Technology」のそれぞれで、答えを出すことを急がずにあらゆる可能性を考慮して、検討を深めていくことである。目先の答えや分かりやすいバズワードに踊らされずに、生活者の心理や企業の経営課題、外部環境などの事実を観察する。そして、仮説構築~検証を繰り返し行い、自分たちなりの戦略を見出していくことが重要である。
今回のモビリティコマースの場合は、多数のデザイン会社との協業、生活者の話を聞き戦略を見直す、人流ビッグデータホルダーとの提携、20社を超える顧客企業とのディスカッション、さらにグローバルでの先進テクノロジー・スタートアップの調査など、多くの取り組みを同時並行で進め、自分たちの戦略を考え見直しながら実行している。
次は、プロセスを実行するために必要な「人・組織」だ。ここでは「小さなコアチームとDDBTそれぞれの専門家ネットワーク」が重要となる。真ん中にコアチーム、それを囲むように、専門家チームのネットワークが構築されるのが理想的だ。
モビリティコマースを例に取ると、コアチームは、NTTデータのコンサルティング事業部が担った。専任メンバーは3名程度だが、この部署にはさまざまなインダストリーの知見を持ったメンバーが在籍している。必要に応じて一時的にアサインするなど、柔軟に連携することで少人数でも力強い推進力を生み出す結果となった。
専門家チームは、デザイン組織だけでなくゲーム会社『株式会社セガ エックスディー』などがデザイン面で参画。データ面ではリアル行動データプラットフォームを運営する『株式会社unerry』との提携。そして、テクノロジーでは、NTTデータの技術革新統括本部に所属するAPG(Agileプロフェッショナル担当)が開発を支援した。

図5:DDBTを活用するために必要な「人・組織」
4.業際ビジネスには想像を超える出会い(セレンディピティ)がある
今回は、 業際ビジネスの推進に必要なケイパビリティDDBTに必要な「プロセス」と「人・組織」について述べた。
NTTデータの業際ビジネスは、まだその一歩を踏み出したばかりだ。さまざまな企業とPoCをさらに進め、事業化を実現していく。難しいのは、それぞれの企業の方針や方向性を取りまとめて、なぜそのビジネスやプロジェクトをやっていくのかを経営目線で説明することだ。経営目線でパートナー企業の本質的な課題を捉えることで、MaaSなどの流行り言葉に一時的に便乗するような取り組みではなく、企業の事業変革につながるような深い連携が可能となる。
実際に業際ビジネスに取り組もうとすると、さまざまな企業との共創が必要になるため、まずは誰と組むべきかと悩まれるかもしれない。目的の領域やプロジェクトに合わせて共創する業種や業態の企業を探しがちだ。
しかし、プロジェクトが動き始めると、自分たちが組みたいと思っていた企業とは異なる意外な出会い、セレンディピティがある。上記の事例でも、これまでお付き合いのなかった企業と偶然の出会があり、そこから生まれた新たな発想もあった。中には、共同でPoCを実施したり、デザイン面での協業に至ったケースもある。
直接的に関係する仲間を見つけるだけでなく、常に胸襟を開き、オープンに連携していくことが、今後重要になるだろう。NTTデータも、こうしたセレンディピティを楽しみながら、DDBTのケイパビリティや推進力を持って共創し、社会を変える新しい価値を生みだしていく未来を見据えている。