データ連携基盤の概要
近年、サステナビリティへの関心や重要性は高まり続けており、サステナブル投資は主流となっています。一方で、普段携わっている業務や技術がサステナビリティとどのように結びつくのか、どのように活かしていけるのか、うまくイメージしきれていない方も多いのではないでしょうか。
この連載では、「技術」観点で、テクノロジー×サステナビリティのトレンドや具体事例などを紹介します。全10個の技術テーマを取り上げており、今回はその最終回としてデータ連携基盤に注目します。近年、企業内外や業界を越えたデータ連携のニーズが高まっており、その技術を活用した業務効率化や資源の最適化に向けた取り組みが進んでいます。本記事では、企業間の連携を支える重要な仕組みとして注目されるデータ連携基盤がサステナビリティと結びつくことで、どのような新たなトレンドや事例が生まれているのかを探っていきます。
データ連携基盤のトレンド
ビッグデータやアナリティクスを含む「データ連携基盤」については多くの市場調査がありますが、今回取り上げる「企業間データ連携基盤」は新しい概念であり、調査・公表された情報がまだ限られています。しかし、近年データ連携基盤に関連した取り組みは国内外で増加しており、それに伴い法規制の整備が進んでいます。
特に欧州ではデータ連携基盤の取り組みが多く見られ、欧州データスペースはEU内でのデータ共有と活用を促進する統一的な枠組みとして注目されています。欧州委員会の政策に基づき、データスペースの技術的側面や運用が着実に進展しており、欧州データスペースを支える技術的基盤として、Gaia-X構想(※1)に基づくプロジェクトも次々と立ち上がっています。
さらに、2023年に施行された欧州電池規制は、電池の持続可能性やライフサイクルに関するデータ管理の強化を目的とした取り組みの一環であり、その実施にはデータ連携基盤の整備が不可欠です。
国内でもさまざまな取り組みが進んでいます。例えば、官民連携の取り組みである「ウラノス・エコシステム」は、企業間でのデータ共有や活用を促進するプラットフォームとして注目されています。さらに、「DATA-EX」は企業間での安全かつ効率的なデータ交換を実現する技術的な枠組みを提供し、データ流通を支える基盤として機能しています。これらの取り組みは、国内におけるデータ連携基盤の整備を加速し、企業のDXを支える重要な要素となっています。
これらの取り組みや法規制の整備によってデータ連携基盤の確立が進み、産業の効率化やイノベーションの促進が期待されます。さらに、SDGsの目標の一つである「産業と技術革新の基盤をつくろう」にも寄与すると考えられます。一方で、データ連携基盤の利活用には電力消費などの環境負荷の問題も伴うため、再生可能エネルギーの利用やエネルギー効率の向上も重要な課題となります。
https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2022/0415/
NTT DATAのデータ連携基盤における取り組み
次に、NTT DATAでのデータ連携基盤に関する取り組みを紹介します。NTT DATAは、データ連携基盤やデータスペースに関連する研究開発を積極的に進めています。具体的な活動としては、共創を通じてのユースケースの創出、接続性などの特性を重視した技術開発、そして異なる基盤(制度や技術等)との相互連携実現に向けた取り組みがあります。
一例として、NTT DATAは再生可能エネルギーを活用した分散型エネルギー資源(DER)の情報流通基盤の構築を進めています。カーボンニュートラル達成にはDERの普及が不可欠ですが、情報流通体制が整っていないと、需給バランスが崩れ、電力の安定供給が難しくなります。NTT DATAは、2025年までに3,000万台のDERから情報を収集し、数秒から1分単位でデータ処理を行うことを目指しています。詳細についてはこちらの記事(※2)をご覧ください。
また、別の事例として、NTT DATAは電動車向けバッテリーのカーボンフットプリント情報の企業間連携を進め、2024年5月からバッテリートレーサビリティプラットフォームの提供を開始しました。この事業は、前述のウラノス・エコシステムのファーストユースケースとして位置づけられています。まずはバッテリー製造時のカーボンフットプリント情報を企業間で安全に連携する機能を提供し、500社以上の企業への利用拡大を目指しています。詳細についてはこちらの記事(※3)をご覧ください。
最後に
テクノロジー×サステナビリティと題して、連載の第9回ではデータ連携基盤とサステナビリティのトレンドを解説してきました。本記事で紹介した内容の詳細に加え、ホワイトペーパーでは他社での事例などについてもまとめています。(※4)
前述の通り、データ連携基盤の活用は、「産業と技術革新の基盤をつくろう」をはじめとするSDGsの目標達成に貢献することができるでしょう。一方で、データ連携基盤の利用には一定の電力を必要とします。そのため、サステナビリティの観点では、今後再生可能エネルギーの利用やエネルギー効率を向上させることも重要な目標となってきます。
データ連携基盤による運用改善などのメリットだけでなく、環境負荷などのデメリットについても理解しながら技術を利活用し、「持続可能な社会」を目指していくことが重要です。

図:ホワイトペーパーの構成
NTT DATAは、「普段業務で活用している技術がサステナビリティにどのように関連するのかを知り、サステナビリティをより身近に感じること」を目的として、全10個の技術テーマについてホワイトペーパーを公開しました。
ホワイトペーパーを通じて、普段接している技術とサステナビリティの関連を深く理解し、日々の生活や業務にその視点を取り入れていただければと思います。

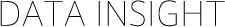



あわせて読みたい: