はじめに~量子コンピュータの概要~
近年、サステナビリティへの関心・重要性は高まり続けており、サステナブル投資は主流となっています。一方で、普段携わっている業務や技術がサステナビリティとどのように結びつくのか、どのように活かしていけるのか、うまくイメージしきれていない方も多いのではないでしょうか。
この連載では、「技術」観点で、テクノロジー×サステナビリティのトレンドや具体事例などを紹介します。全10個の技術テーマを取り上げる予定であり、今回は量子コンピュータに注目します。量子コンピュータは量子力学に基づいた情報処理により、従来のコンピュータでは難しい複雑な計算を高速で行うことができ、多岐にわたる分野で活用されはじめています。現在注目されている量子コンピュータ技術とサステナビリティをかけ合わせた時にどのようなトレンド、事例があるのか見ていきます。
量子コンピュータのトレンドと市場規模
世界の量子コンピュータ市場は拡大傾向にあり、2032年までに126億2,070万ドルに成長すると予測されています(※1)。この市場拡大の背景には、量子コンピュータが単なる高速計算処理にとどまらず、エネルギー消費の最適化、気候変動の予測や対策、新しい材料や新薬の開発など、環境負荷の軽減や社会課題の解決に活用されている点があります。また日本においても、量子コンピュータ市場は拡大を見せています。日本政府は、量子コンピュータを含めた量子技術を「新たな価値創出のコア」と位置付け、2016年から積極的に推進しています。その中で2022年には「量子未来社会ビジョン」を策定し、2030年に目指すべき状況として「国内の量子技術の利用者を1,000万人に」「量子技術による生産額を50兆円規模に」「未来市場を切り拓く量子ユニコーンベンチャー企業を創出」の3つを掲げています(※2)。
こうした動きの中で企業は、量子コンピュータの技術を駆使してイノベーションを加速させるとともに、環境や社会に配慮した持続可能な成長を実現するための社会的責任を果たすことがより重要となるでしょう。
https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/量子コンピューティング市場-104855
https://www8.cao.go.jp/cstp/ryoshigijutsu/240409_q_measures.pdf
NTT DATAの量子コンピュータにおける取り組み
量子コンピュータは、膨大な計算パターンを並列処理できるため、複雑な最適化問題を効率的に解決するこができます。
NTT DATAでは、この量子コンピュータ技術を活用して、サステナブル社会の実現にもつながる最適化への応用に取り組んでいます。具体的な事例として、NTTデータイタリアでは、CO2回収および変換を効率的に行う触媒開発に向けて、量子機械学習手法および分析用シミュレーションツールの研究開発を進めています。この取り組みはパレルモ大学およびマグナ・グラエキア大学と共同で行っており、NTT DATAは本プロジェクトの成果を用いて、気候変動への取り組みや温室効果ガス排出量の削減、創薬など他分野への応用を進めています。
また、匂いの再現を行うために量子コンピュータを活用しています。匂いを再構成するためには、元となる匂いを数値化し、あらかじめデータベース化しておいた膨大な量の香料化合物の中から組み合わせる必要があります。そこでNTTが研究開発しているイジングマシンの「LASOLV」を活用することで最適な組み合わせを数十秒で計算し、リアルタイムで匂いを再現することが可能になりました。この技術により、VRやメタバース、イベントなどでの新たな匂いの体験を提供できます(※3)(※4)。
さらに、広島大学と共同で「順列型組合せ最適化問題」(=n!通りある順列の中から最適なものを選ぶ問題)を解く新手法「dual-matrix domain-wall法」を開発しました。製造業などの物流や人員配置には膨大なパターンが想定されますが、今回開発した手法では順列生成イジングモデルのサイズを大幅に削減し、計算処理の精度を向上させることに成功しました。これにより、物流や人員配置の最適化が進み、労働環境の改善や温室効果ガス排出量の削減にも貢献することが期待されています。NTT DATAはこれらの技術を活用し、お客さまの業務改善案件で、2026年までに100件以上の受注を目指しています(※5)。
https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2024/0328/
~従来比8倍規模の組合せ最適化計算を実現することで、新たな匂いビジネス創出へ~
~モデルサイズの大幅削減等によりイジングマシンや量子アニーラーで解ける問題範囲を拡大~
おわりに
テクノロジー×サステナビリティと題して、連載の第5回では量子コンピュータとサステナビリティのトレンドを解説してきました。本記事で紹介した内容の詳細に加え、ホワイトペーパーでは量子コンピュータを活用したエネルギー開発研究や、人流の最適化による災害時の被害の抑制に関する他社事例等についても紹介しています(※6)。
量子コンピュータの活用は、「産業と技術革新の基盤を作ろう」をはじめとするSDGsの目標達成に貢献することができるでしょう。一方で、量子コンピュータの利活用にはエネルギー消費による環境負荷の問題も伴うことに注意が必要です。量子コンピュータを活用した運用には多くのエネルギーを必要とする冷却技術や、量子ビットの安定性を保つための高度な技術が必要になるため、サステナビリティの観点では、再生可能エネルギーの利用やエネルギー効率を向上させることも重要な課題となってきます。量子コンピュータ利活用によるメリットの側面だけでなく、環境負荷などのデメリットについても理解しながら技術を利活用し、「持続可能な社会」を目指していくことが重要です。

図:ホワイトペーパーの構成
NTT DATAでは、「普段業務で活用している技術がサステナビリティにどのように関連するのかを知り、サステナビリティをより身近に感じること」を目的として、全10個の技術テーマについてホワイトペーパーを作成、公開予定です。
次回以降、スマートロボットやデジタルヒューマン、メタバースといったテーマについて取り上げる予定です。ご期待ください。

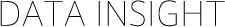



カーボンニュートラルについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/carbon-neutral/
量子コンピュータ・イジングマシンについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/quantum/
あわせて読みたい: