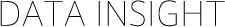- 目次
システム開発の高速化、可視化を実現するローコードプラットフォーム
従来、システムを開発する際はプログラミング言語でソースコードを書く必要があった。そのため高度な専門的知識を必要とし、開発期間は長期に及ぶことが多く、エラーが発生しやすい、変更が困難といった課題もあった。
これに対し、プログラミングの専門知識を持たない人でも短期間でシステムの開発をできる手法が「ローコード開発」だ。画面上に表示されるアイコンやメニューなどを組み合わせてシステムを開発できるので、必要最小限の知識でビジネスユーザーでも簡単に操作ができる。システム開発の効率化、高速化ができる手法として、近年注目を集めている。

図1:ローコード開発とは
ローコード開発を取り入れるメリットとデメリットについて、NTTデータ 技術革新統括本部 システム技術本部 部長の市川耕司は、次のように解説する。
「エンジニア視点でのメリットは、プログラミングの作業量が減り、開発スピードを速められる点、設計が見える化できる点が挙げられます。一方で、ローコード開発ならではの作法を覚えなければならない点、技術的な制約がある点はデメリットといえるでしょう。しかし、今後は多くの企業でローコード開発を取り入れるケースが増えていくとみられており、使いこなせないエンジニアは取り残されてしまう可能性があります」(市川)

図2:ローコードプラットフォーム導入のメリット
では、プロジェクトを統括するマネージャーの視点でローコード開発を導入することのメリットとデメリットは、何が挙げられるのだろうか。
「まず、ローコードプラットフォームはクラウドベースなので、クラウドネイティブな開発・運用が可能となります。プラットフォーム自体が進化していくため、技術進化の恩恵を受けられる点は大きな魅力です。デメリットは、クラウドベースの新しい考え方を導入するための社内説明が大変である点、プログラミングの専門知識が不要とはいえ、一定の社員教育が必要となる点は負担になるかもしれません」(市川)

技術革新統括本部 システム技術本部 部長
市川 耕司
こうしたメリットとデメリットがあることを踏まえた上で、市川は続ける。
「アナリスト等の情報による、今後ローコードプラットフォーム市場の成長率は20~30%で伸びていくとみられ、広く普及していくと予想されています」(市川)
ローコードプラットフォーム市場が成長する背景には、企業のDXやIoT化によってアプリケーション開発のニーズが爆発的に増えている一方で、開発できるエンジニアが不足しているという現状がある。また、ビジネスにおいてスピード感と柔軟性が求められるようになり、短期間でのアプリケーションの開発が必要とされるようになったことも、背景として挙げられる。
市川は、「ローコードプラットフォームを使いこなすための最初の準備は大変ですが、うまく活用することで大きな恩恵を得られます。ビジネスとITを一体化して事業を広げていくためにも、ぜひ活用を検討してほしい」とすすめた。
ローコードプラットフォームを取り入れるための留意事項
ローコードプラットフォームを活用して開発を行うためには、大きくわけて4つの留意すべきポイントがある。
1つ目が、製品仕様の制約があること。専門知識がなくても開発できることの裏返しとして、動作対象OSやデータベースに制限があるほか、カスタマイズ、拡張言語に制限が出てしまうのだ。また、プラットフォームのバージョンアップの際には改修が必要となることもある。
2つ目が、ライセンスに制約があること。データベース容量、1日あたりの要求数が制限されることに加え、プラットフォーム側の都合による費用変動リスクがあることを覚えておかなければならない。
3つ目の留意点は、アプリケーション基盤要素の検討が必要なこと。ローコードプラットフォームを使うことで画面を使って簡単にシステムやプログラムをつくることはできる。しかしそれとは別に、製品トランザクション仕様やセキュリティ設定、アクセス制御などは従来のシステム開発同様独自で検討する必要がある。
そして最後に、製品トラブル対応には限界があることも知っておかなければならない。プラットフォーム自体にバグが発生したり、ユーザーが突然ログインできなくなったりしたときに、自社だけではトラブルを解決できないことも起こりうる。

図3:ローコード開発を進める際の留意事項(例)
市川は、「ローコードプラットフォームを導入する際には実現できることに制限があることを理解し、適切に活用していくことが必要です」と語る。
ローコードプラットフォームには、大きく3つのカテゴリがある。専業ベンダーが提供する製品、MicrosoftやSalesforceといったSaaS、PaaSベンダーが提供する製品、ビジネスプロセスマネジメント系ベンダーが提供する製品だ。それぞれの特長を知った上で自社にあった製品を選ぶことが大切である。
レガシーシステムをローコード開発でリプイレス。東日本電信電話の事例
NTT東日本では、社会的な影響のあるインシデントが起きた際に迅速な情報発信を行うために、危機管理の仕組みの刷新にあわせて、経営層による緊急情報把握を速やかに行うためのシステムを開発した。従来のレガシーシステムはブラックボックス化していたため、ローコードプラットフォーム「OutSystems」を活用してリプレイス。社員数人が開発担当となり、内製化することになった。
そのメンバーの1人、デジタル革新本部 企画部ソフトウェア内製化推進PT 課長の神山和憲氏は、プロジェクトが開始したときのことを次のように振り返った。

東日本電信電話株式会社
デジタル革新本部 企画部ソフトウェア内製化推進PT 課長
神山 和憲 氏
「既存システムを刷新するにあたり、内製でリプレイスしてみようとプロジェクトがスタートしました。まずは『OutSystems』が提供する研修を受けたのですが、それだけでは我々だけで開発するのは難しいと感じました。これまでシステム開発は外部ベンダーへのアウトソーシングが基本でした。そのため、リプレイスするにあたって既存システムの分析をどう進めるか、分析した上でどのようなスキーム、プロセスで開発していけばいいのかがわからないといった課題に直面しました」(神山)
NTTデータでは社内ルールにあわせたプロセスを整備し、技術面をサポート
そこで、サポートとして協力することになったのがNTTデータだった。プロジェクトに参画した技術革新統括本部 システム技術本部 課長代理の島倉優人は、「開発プロセスの整備」と「技術的な課題のサポート」の2点を中心に支援を行ったという。
「1つ目の『開発プロセスの整備』という点では、NTT東日本の社内文化やルールにあわせた形でのソフトウェア開発プロセス整備を意識しました。ローコードプラットフォームを導入したときに、運用がボトルネックになることで内製化の取り組みが進まなくなることは避けなければなりません。お客さま企業が自律的にソフトウェア開発のライフサイクルを回せるプロセスが必要だと考えました」(島倉)
プロセスを整備しすぎると内製化の良さでもある自由度が下がってしまう。スピーディーに開発を進めるためには、何も制約を設けることなくメンバーの裁量で進めることが理想的だ。しかし、その反動として、将来的にガバナンスがきかなくなる可能性もある。島倉はNTT東日本の社内文化に合わせて、裁量に委ねる部分とガバナンスをきかせる部分のバランス取りながら開発プロセスの整備を進めた。
2つ目の『技術的な課題のサポート』については、次のように振り返った。

技術革新統括本部 システム技術本部 課長代理
島倉 優人
「先ほど紹介されたローコードプラットフォーム導入の留意点の1つに、『AP基盤要素の検討』がありました。今回のプロジェクトでも、ガバナンスを担保するアーキテクチャ設計だけでなく、東日本電信電話の社内ルールに準じたセキュリティの設定が必要でした」(島倉)
具体的には、社内のセキュリティルールに準じて「OutSystems」を利用するために不足していることをリストアップし、セキュアログイン認証機能の実装や、アプリケーションログの管理手法の確立、アプリケーションユーザーの管理を効率的に実施できるアプリケーションの実装を実施。また、「OutSystems」単体では難しい要件を実現するために、AWSとの連携もサポートした。
「アプリケーションの性能問題が発生した際には、NTTデータ側でボトルネックを特定し、どのように実装を変更すれば解決するかの具体的な方法を提案して、解消に導いたこともありました」(島倉)
さらに、既存システムから「OutSystems」へ移行する際には、データ移行アプリケーションを提供。NTTデータのこれまで培ったソフトウェア開発力を生かし、東日本電信電話だけでは対応が難しかったIT全般における高度な技術的サポートを行ったのだ。
自分たちでつくることで、コストを抑えながら柔軟な開発を実現
プロジェクトを進める中で島倉が意識したのは、「お客さま自身が楽しく開発できること」だったという。密にコミュニケーションを取り、質問しやすい雰囲気をつくりながら、お客さま自身がものづくりを楽しんで進めることで、次の内製化プロジェクトにもつながっていく。
こうしたNTTデータの支援に対し、神山氏は「自分たちでアプリケーションをつくったことで、メンバーの会話も変わってきました」と振り返る。
「以前は、『アウトソーシングの発注先をどこにするか』『なぜその価格なのか』といった話が多くなりがちでした。しかし内製化を進めてからは、『どうやったらこの機能をつくれるか』『もっとこうしたらよくなるのでは』といった話をする機会が増えました。自分たちでつくることで、何をどうやったら動くのかなどシステムの仕組みがわかるようになったため、自信を持って開発を進められるようになりました」(神山氏)
アウトソーシングの場合は発注先に要望を出し、しばらくしてから修正版があがってきます。一方内製化の場合は、社内で出た要望をすぐに反映し、試作品をその場で確認することもできる。開発期間を短縮しながら、社内の細かいニーズに対してより柔軟に、すばやい対応が可能となるのだ。神山氏は「結果的に、アウトソーシングするよりも5分の1程度のコスト低減につながりました」と話す。社内でも好評で、内製化してローコード開発することの意義を見いだせたという。
プロジェクトとしては成功したが、課題も残る。神山氏は今後について、「内製化した実績ができたことで、社内からこういうのをつくれないかと相談されることが増えました。今後のシステムの維持運用を考えても、対応できる人数を増やし、体制を強化することが必要です。そこで、内製化のチームの延長線としてオフショア“拠点”を強化しています。オフショア“先”ではなく“拠点”として、技術力は自社に持ったまま、拠点を増やしていくようなイメージです」と見通しを語った。
今回の「OutSystems」を活用した内製化プロジェクトでは、すでに1つのアプリケーションをリリース済みだ。現在は、すでに次のフェーズに進んでいるという。
「NTT東日本様と今進めているのが、『OutSystems』の取り組みをさらに発展させたCoEの仕組みづくりです。今後もNTTデータでは組織づくりのコンサルティングなど幅広い支援を続けていく考えです」(島倉)
本記事は、2023年1月24日、25日に開催されたNTT DATA Innovation Conference 2023での講演をもとに構成しています。