- 目次
IT自体の環境負荷問題が顕在化
「サステナブルIT」とは、ITのライフサイクル全体での環境負荷低減やAIの倫理的な活用など、サステナビリティの視点から見直す考え方です。特に環境視点では、ITの需要が増え始めた1990年代から、データセンターの消費電力やIT機器の製造・廃棄といった課題が指摘され対応が続けられていましたが、多くの企業で温室効果ガス排出量の算定や報告が進められるようになったことで、再び注目が集まるようになっています。
特に、デジタル化や生成AI活用の広がりが、こうした課題をより際立たせていると小林は説明します。

「生成AIを試しに使ってみているという企業は非常に多いと思いますが、活用が進むことで、社会全体の電力消費量が急拡大すると言われています。電力消費量の増大は温室効果ガス排出量の増加に直結するため、企業がITを活用して業務や働き方を効率化しても、それが温室効果ガス排出量の削減につながらないということになってしまうのです。ほかにも、データ取得後に活用されないまま保存されている、いわゆるダークデータに掛かる無駄な電力消費やコストの問題、IT機器に使用されるレアメタルの枯渇問題など、環境に関する課題が議論されています。
もう1つあるのが、社会的な課題です。生成AIを活用する際の著作権やプライバシー侵害、情報漏えい、誤情報といった倫理面への対策も改めて求められるようになっています」

図1:サステナブルITが求められるようになった背景にある課題
サステナビリティ経営の取り組みの有無が企業のブランド価値を左右する
デジタル化により、業務効率化や働き方の多様化、新しいサービスの創出など、企業は多くの恩恵を受けてきました。そして、労働人口減少への対策が急務となる今、生成AI活用がその解決を導く方法として多くの企業の期待を集めています。
小林は、「今後もITの恩恵を享受し続けるには、それに伴う責任をきちんと果たしていく必要がある」と指摘します。
加えて、環境・社会・ガバナンス(ESG)への取り組みを経営戦略に盛り込み、サステナビリティ経営への対応の有無が、企業のブランド価値や投資家の評価を左右する時代になってきました。調達においては、環境に配慮した製品やサービスを求める企業が増えており、特にグローバルの大手企業ではその要求が高まっています。また、従業員の定着率にも影響が大きいと小林は説明します。
「グローバルの従業員などは特に、サステナビリティに取り組んでいない会社では働きたくないという意識も高まっています。真摯にサステナビリティ経営に取り組むことが、人材確保という面でも有効です。日本も徐々にそういった形に変わっていくでしょう」
ITの環境負荷を抑える対策とは
では、ITが環境や社会に与える負荷に対して、企業はどのような対策が取れるのでしょうか。
データセンターやネットワークといった「インフラ」やIT機器などの「ハードウエア」であれば、グリーン調達の考え方を適用することが有効です。同じタスクでも低消費電力で実行できる省エネ性能の高いサービスや機器、環境に配慮して製造された機器を選択することが、サステナブルITの実現につながります。
例えば、生成AIやクラウドサービスへ電力を供給するデータセンターは、再生可能エネルギーを活用して運用されているものも増えており、そうしたデータセンターを活用することが対策の1つとなります。

図2:ITシステムのレイヤーに対してサステナブルITの対策を実施
さらに今、脚光が集まるのが「ソフトウエア」の領域です。ソフトウエアの環境負荷は把握しづらく、これまではあまり注目されていませんでした。しかし、今後、大きく改善が見込める領域だと小林は話します。
「車の運転をイメージしていただくと分かりやすいでしょう。全く同じ車で同じ経路を進んだとしても、ドライバーの運転によって燃費が良くなったり、悪くなったりします。それと全く同じことがソフトウエアでも言えるのです。
例えばAIのモデル開発では、学習のプロセスで多くの電力を消費するため、生成AIの学習を再生可能エネルギーによる発電が多い時間帯や地域で行うようにスケジューリングするソフトウエア技術も登場しています。一方で、ソフトウエアは5年などのロングスパンで運用していくため、ストレージの交換や廃棄といった観点でも、無駄なストレージ利用を減らすソフトウエア設計・実装などが有効です」
ソフトウエアの環境性能評価の仕組みづくりにNTT DATAも参画
NTT DATAは、2040年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることをめざす「NTT DATA NET-ZERO Vision 2040」を掲げており、ITそのものの環境対応の必要性にいち早く着目し、取り組みを進めてきました。一例が、グローバルで進むサステナブルITに関する2つの団体での活動です。

図3:2つの団体は異なるアプローチでサステナブルITのためのルールづくりなどを進めている
まずは「Green Software Foundation」(以下、GSF)(※1)。GSFは、2021年5月に設立された非営利団体で、グリーンなソフトウエア開発に必要となるルールづくりや開発ツール・ベストプラクティスの策定、さらには業界への普及展開をミッションとしています。
NTT DATAは、GSFが設立した後の2021年9月に、アジアの企業で初めて活動に参画しています。ソフトウエアを利用する際の環境性能を評価する方法の策定や、実際の業務で活用できるオープンソースソフトウエアなどの開発を手掛けてきました。
サステナブルITに関するこうした取り組みは他に例がなく、技術的にも高い専門性が求められる難しい領域だったと小林は説明します。
「ソフトウエアを改善していこうと思ったときに、それまでは、総合的な環境性能を測る実用的な評価手法が定まっていませんでした。温室効果ガス排出量を把握する場合、販売金額に係数をかけるという一般的な評価方法だと、どんなに環境性能が良くても、環境に配慮していないソフトウエアと値段が一緒であれば、排出量が同じという評価になってしまう。そうなると、環境性能の高いソフトウエア開発への努力は進みません。
価格に関係なく、環境に配慮したことがしっかりと評価される仕組みづくりをすることで、ソフトウエア業界全体が良い方向に変わっていく必要があるとの思いで、NTT DATAの国内外のエンジニアが連携し標準化活動に取り組んできました」
2021年12月には、Software Carbon Intensity(以下、SCI)のα版を発表。SCIは、ソフトウエア利用時の炭素排出を構成する電力、電力の炭素強度、ハードウエア利用量にもとに、炭素排出量をスコア化する評価手法です。同じ機能を持つ複数のソフトウエアの環境負荷を比較したり、ソフトウエアに加えた改修が炭素排出量に与える影響を把握したりすることができます。
もう1つNTT DATAが参画する団体が、「SustanableIT.org」です。グローバル企業の経営層が参加し、サステナブルITに関するガバナンスのフレームワークを議論しているほか、先進的な知見や各社の取り組み事例を共有し合っています。
エンジニアリング視点と経営視点という異なるアプローチをする2つの団体に加盟することで、少しでも多く実務に取り入れられる知見を得られるように取り組んでいます。
ISO採択で活用が広がるSCI
GSFでの標準化活動や、SustainableIT.orgでの経営者層に向けた技術情報の提供といった草の根活動が、今、結実し始めています。
2024年5月に、SCI 1.0版(2022年12月に発表)が国際規格「ISO/IEC 21031:2024」として採択されたことで、世界のソフトウエア業界での活用が着実に広がろうとしています。(※2)
さらに、同年9月には、SustanableIT.orgが運営するSustainableIT Impact Awards 2024で、NTT DATAがガバナンス賞を受賞。SustainableIT Impact Awardsは、ITのサステナブル化に大きく貢献したリーダーや組織に与えられます。(※3)
「企業に求められる環境対応のさらに一歩先を見据えて、GSFにおいて自ら標準化活動に取り組み、さらなる削減に向けた技術開発に取り組んでいる点が評価されました。アジアの企業が表彰されることは少なく、表彰式に参加した際には多くの皆さんからの祝福を受けました」

SustainableIT Impact Awards 2024表彰式にて
動きだした日本市場でのサステナブルIT
海外と比べてサステナブルITの認知度がまだ低い日本でも、NTT DATAは同じ志を持つ企業と協力して普及に向けた活動を展開しています。
その1つが、ソフトウェア開発により排出される温室効果ガス排出量を評価する手法の確立です。NTTグループやNTTの研究所のほか、NEC、日立製作所、富士通といった国内の有力ITプレイヤーが集まり一緒に取り組んでいます。2023年度には経済産業省の事業にも採択され、同省が公表する「カーボンフットプリント ガイドライン」に整合した算定および比較ができるようルール化を行いました。(※4)この取り組みは、2025年1月にLCA日本フォーラム会長賞を受賞しています。(※5)
「企業は、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量を把握し開示する必要がありますが、調達した製品一つ一つのカーボンフットプリントを精緻に把握し、評価する方法が求められています。この仕組みの実現にはITの力が欠かせません。企業の取り組みがしっかりと評価されるように取り組んでいます」
海外で確立したソリューションを日本企業に提供
NTT DATAでは、サステナブルITに関する活動を通して得た知見を生かし、ITのサステナブル化を実現するワンストップソリューションを提供開始しており、海外では、SCIのフレームワークを活用した顧客事例も生まれています。

図4:NTT DATAが提供するサステナブルITに関するサービス
日本国内では、2024年7月から、IT領域のサステナビリティの現状可視化から改善提案までを支援する「サステナブルIT診断コンサルティング」の提供をスタートしました。(※6)お客さまの環境をヒアリングし、5つの領域(IT戦略/ガバナンス領域/デバイスマネジメント領域/アプリケーション領域/クラウド領域/インフラ領域)で、ITのサステナブル成熟度を評価するとともに、ロードマップを策定して、最適なITのサステナブル化をご提案しています。ITシステムの各工程にサステナビリティの観点を組み込むための入り口となるソリューションとして、今後、多くの顧客企業に活用していただくことを見込んでいます。
「サステナブルITを、単なる環境対策ではなく、『ITを活用した』持続的な事業成長に不可欠な要素として、日本企業の皆さんとも一緒に盛り上げていければと思っています」
NTT DATAでは、さまざまな企業との連携を通して、日本企業がサステナブルITを導入するための支援を展開し、これからもお客様の課題解決に貢献してまいります。

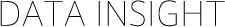



「サステナブルIT診断コンサルティング」の提供を開始についてはこちら:
https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2024/072501/
SustainableIT Impact Awards 2024を受賞についてはこちら:
https://www.nttdata.com/global/ja/news/topics/2024/092600/
サステナブルITは喫緊の課題 ITで新しい仕組みや価値を創造 - 日経ビジネス電子版 Specialについてはこちら:
https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/25/nttdata0306/
あわせて読みたい: