- 目次
70年分のノウハウを生かしたデータドリブン経営を目指して
電源開発株式会社(以下、J-POWER)は、70年以上にわたり発電事業を展開してきた、言わずと知れたエネルギー企業だ。火力、水力、風力といった多様な発電所を国内外で運営し、それぞれの分野で膨大なデータとノウハウを蓄積してきた。
ところが、この豊富なデータを経営レベルで生かしていく体制は、これまで整えられていなかったという。同社でDXを長年推進してきたデジタルイノベーション部 DX推進室長 田中 克郎氏は当時の課題感をこう語る。

電源開発株式会社 デジタルイノベーション部 DX推進室長
田中 克郎 氏
「電子化していないものも含めて、1952年の創業時からのデータが社内に蓄積されているものの、それらを活用して発電所運用の効率化を目指すなど、経営に生かすことができていない状況でした。データドリブン経営を目指そうにも、長年の経験や勘に頼る習慣が事業部全体で多く見られていたのです。データを用いた合理的な判断を実践できる社内文化を築かなければならないと考えました」(J-POWER・田中 氏)
J-POWERは2019年にデジタルイノベーション部を立ち上げ、全社的なDX推進を始動。同部門はデータドリブン経営の実現を目指し、業務プロセスの変革や、社員全体のデジタルリテラシー向上に取り組んでいる。しかし、データ活用を推進していくには多くの障壁があった。
個々人のビジネス理解をいかにデータに落とし込めるかが課題に
まず課題に挙がったのは、属人的なデータ管理や分析が常態化していることだった。
同部署に異動する以前は火力部門に所属していたデジタルイノベーション部 DX推進室 室長代理 宮本 年史氏が、現場でのデータ分析についてこう説明する。

電源開発株式会社 デジタルイノベーション部 DX推進室 室長代理 兼 AI・先端技術 総括マネージャー
宮本 年史 氏
「たとえば、『直近一カ月の火力発電所の熱効率』を調べるとしましょう。まず、各システムから必要なデータをダウンロードしてExcelで集計、分析し、報告書にまとめます。ここで起きる『分析の過程』は人に見せる必要がありませんから、第三者から見ればただの数字だけのシートになってしまい、引き継ぎが困難になりがちです。当時の私は、場当たり的なデータ分析にとどまってしまい、ノウハウの共有や深い洞察にまでたどりつくことができていませんでした」(J-POWER・宮本 氏)
さらに、「データ分析を担う”人財育成”も熟慮すべきポイントだった」と、同部門の服部 啓之氏は語る。同社の事業は多岐にわたるため、少数のデータサイエンティストにすべての分析を任せることは不可能だ。全社でデータ活用を推進していくためには、現場の担当者一人一人がデータを使いこなせるようになることが必要だったという。

電源開発株式会社 デジタルイノベーション部 DX推進室 兼 イノベーション推進部 企画室 主任
服部 啓之 氏
「発電所の運営において、各部門は専門的な知識を駆使して取り組んでいます。しかしながら当社は人事異動も多く、ノウハウが定着しづらい環境であることもデータ活用が進まなかった要因です。個々人が現場で得たビジネス理解をどうすればデータにうまく落とし込めるか。どうすればExcelではできない高度な分析を、誰もが負担なくできるようになるか。こうした課題感を出発点に、2023年からデータ分析ツールの検討を始めました」(J-POWER・服部 氏)
社員が自主的に使える最適解としてデータ分析ツール「Alteryx」を導入
J-POWERから「どのツールを導入すべきか、専門家としての意見を聞きたい」と相談を受けたNTTデータ 鍋山 大志が提案したのは、データ準備や前処理、共有まで一気通貫で行えるデータ分析プラットフォーム「Alteryx(アルテリックス)」だった。

NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 インダストリセールス事業部
鍋山 大志
「当初は別の製品についてお問い合わせをいただいたのですが、『事業部側で自立的に分析できるツール』という理想を伺ったとき、Alteryxが最良だと考えました。Alteryxは直感的な操作で誰もがデータの加工や分析ができるツールであることに加え、基礎レベルから応用レベルまで、オンライン研修やユーザーコミュニティなどの学習コンテンツが豊富だからです」(NTTデータ・鍋山)
J-POWERの田中氏、宮本氏、服部氏は、それぞれAlteryxに初めて触れた時の印象を次のように振り返る。
「分析フローがグラフィカルに可視化されているため、どんな処理が行われているのか一目瞭然な点がとても良いと感じました。Excelを使用する社員なら誰でも使用できるだろうと感じるユーザビリティが、導入の足掛かりになりました」(J-POWER・田中 氏)
「実際にフローをつくっていると『何を行っているのか』がロジカルに見えるので、頭の中がクリアになっていく感覚があります。また、どんな処理が行われているのかが一目で分かるので、少し時間を空けてからファイルを確認してもすぐに追いかけられる点が魅力的です」(J-POWER・宮本 氏)
「分析をAIで自動化できるようなツールも検討していたのですが、自動化してしまうのではノウハウが蓄積できません。Alteryxは自ら手を動かす中でも直感的に『使いやすい』と感じることができ、ユーザーフレンドリーであると感じました」(J-POWER・服部 氏)

ツール導入のみならず社内でのデータ分析「CoE」構築も提案
さらにNTTデータは、事業部側で自主的に分析できるツールとしてAlteryxを提案するだけでなく、社員のデータ活用を浸透させていくためにデータ分析CoEの構築も提案。この提案を受け、J-POWER 服部氏は「まさに我々が目指していた、社内のデータ活用文化の醸成につながる」と共感したという。Alteryxの拡大支援を担当するNTTデータ 大長 純平は提案した理由をこう述べる。

NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルティング事業部
大長 純平
「『ツールを導入したものの、ユーザーに広がらない』という失敗例も数多く見てきました。データ分析CoEとは専門的な知識・技術を集約し、全社横断でデータ活用を支援する組織のことです。データドリブンな社風を醸成するためには、単にAlteryxの操作方法をお伝えするだけでなく、データ分析CoE構築もサポートしていくことが重要だと考えました」(NTTデータ・大長)
NTTデータの提案した「Alteryxの導入」と「データ分析CoE構築のアプローチ」は、J-POWERの組織文化やDX推進の方向性に合致。こうして、J-POWERはデータ活用の基盤となるツールと、活用・推進の両面での支援を行うパートナーにNTTデータを選び、両社はデータドリブン経営の実現に向けた一歩を踏み出した。
NTTデータの支援で広がる、データ活用の可能性
Alteryxの導入後、NTTデータは基礎的な使い方を教える研修を実施するとともに、隔週で相談会を開催。社員の具体的な悩みを受け、Alteryx活用のサポートを行っている。データサイエンティストとして相談会を主導するNTTデータ 近藤 立志は、「社員に楽しんでもらうこと」を心掛けているという。

NTTデータ テクノロジーコンサルティング事業本部 デジタルサクセスコンサルティング事業部
近藤 立志
「新たなツールの導入は、既存の業務をガラリと変える試みです。社員の皆さんが主体的に取り組んでいただくためには、まずは『楽しい』と感じてもらうことが重要だと考えています。また、ただ使い方を教えるのではなく、その背景にある業務課題をヒアリングし、その解決策としてAlteryxをどう活用すべきか、総合的な視点を持って相談会を実施しています」(NTTデータ・近藤)
さらに、相談会の中から新たな洞察の芽が生まれようとしていると、J-POWERの服部氏は言う。
「Alteryxは、外部データを整えて一元的にまとめてくれる機能があります。発電事業は気象情報と密接な関係がありますから、こうした機能を活用して、世界各国の気象データを取りそろえて分析すれば、発電効率向上につながるヒントが見えてくるでしょう。このような幾つもの試行錯誤が、近い将来、各事業部内で生まれてくると思います」(J-POWER・服部 氏)
“CoEの自走化”に向け、ツール活用にとどまらない連携を強化
J-POWERの本格的なデータ分析CoE立ち上げは2025年度を予定しており、現在NTTデータとの密な連携を重ねながら、ロードマップの策定を進めている段階だ。また、Eラーニングを中心としていたDX人財研修においても、今後さらに拡充予定である。
「2024年はJ-POWERの全社2000名超およびグループ各社に対して、DXリテラシーに関するEラーニングを実施しました。来年度からは、中核人財や高度専門人財を育成するために、Alteryxを用いた高度な分析トレーニングや機械学習などの教育プログラムを提供していきます」(J-POWER・田中 氏)
将来的には事業部ごとにAlteryxによる分析を深化させていってほしいと、J-POWER 宮本氏、服部氏の両名は展望を語る。
「今は現場の要望に応じて、Alteryxによる分析の方法をDX推進室が伝えている状況ですが、今後は現場主体のデータ活用が発展していくことを期待しています。火力、水力、風力で仕事のやり方や留意すべきポイントは異なりますから、それぞれに合った分析手法を確立してもらえるよう、サポートを行っていきます」(J-POWER・宮本 氏)
「ゆくゆくはAlteryxに詳しい人が集まった『ミニCoE』が事業部ごとに現れていくことが理想です。財務系のデータなども組み合わせて、より経営に活用できるよう取り組んでいきます」(J-POWER・服部 氏)
J-POWERが目指す最終ゴールは“データ分析CoEの自走化”だ。さらなるデータ活用の発展を支える立場として、NTTデータ 鍋山はこう意気込んだ。
「データ分析CoEを社内で確立するためには、現段階のツール活用・推進におけるサポートだけでなく、どのように活動をスケールさせていくべきか、『実際に業務が改善できた』というユーザー体験をどうやって増やしていくか、次のステップの支援も必要になっていきます。J-POWER様のデータドリブンの実現に向け、引き続きさまざまなサポートを行っていきます」(NTTデータ・鍋山)
両社の強いつながりが、J-POWERの新たな可能性を切り開いていくことだろう。

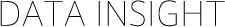



Alteryxについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/alteryx/
あわせて読みたい: