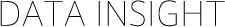いま脳科学が注目される理由
感情から行動まで、そのメカニズムを解き明かす
───なぜ、いま脳科学に注目が集まっているのでしょうか。
いま、世界の名だたる企業は脳科学の知見をビジネスに取り入れるべく、活発に研究を続けています。その背景にあるのは、私たちの意思決定や行動の内、実に9割以上が無意識で行われており、意識によって決定される割合は1割に満たないことが近年の研究でわかってきたこと。その無意識下のメカニズムを解明することで、製品やサービスの開発、さらに人材育成につなげようというのが大きな狙いだと言えます。

萩原一平(はぎわら・いっぺい)NTTデータ経営研究所 研究理事、情報未来イノベーションセンター長。電機メーカー、シンクタンク勤務を経て、1997年より現職。専門分野はニューロコンサルティング、新規事業化支援、マーケティング戦略、環境分野全般、地域情報化、ヘルスケアなど。現在、応用脳科学コンソーシアム事務局長、横浜国立大学大学院環境情報学府客員教授、大阪大学招へい教授。主な著書に『脳科学がビジネスを変える』『ビジネスに活かす脳科学』(日本経済新聞出版社)などがある。
では、なぜこのタイミングで注目が高まっているのか。背景としては、2つの技術的な発展が挙げられます。1つは、脳活動の計測技術の進歩です。具体的には、fMRI(機能的MRI)(※1)の登場が何といっても大きいでしょう。MRI(核磁気共鳴画像装置)は通常、身体内の断面構造を画像化する装置として使われていました。そこに進展をもたらしたのは、アメリカのベル研究所に勤務していた小川誠司氏が考案し開発した、脳内の動的な血流変化から部位ごとの活動を計測する技術です。この仕組みを用いたfMRIの登場によって、脳を侵襲する(傷付ける)ことなく高精度に、脳活動を可視化することができるようになりました。
そしてもう1つが、計測で得られた情報を処理する技術です。IT、とりわけAI関連技術の目覚ましい発達によって、脳の3次元構造上における微細な反応を高速で解析することができるようになりました。
これらをはじめとするこの10年ほどの技術の進歩によって、脳科学は医学分野のみならず、産業応用や人材育成などの分野においても有益な、様々な知見を創出し始めています。
───脳科学によって、どのようことがわかるのでしょうか。
ひとことで表すなら、人間の感情や意志決定、行動の仕組みなどを理解できるようになります。
「脳は人間の司令塔」と言われますが、人間の感情や意思決定、その結果である行動はすべて脳の指令によるものです。私たちが生命を維持しているのは、脳が休みなく働き続けているからです。例えば、眠っている間も脳の記憶領域では1日に得た様々な情報を整理しています。こうした脳の機能メカニズムを解明し、社会に役立てることが脳科学の使命です。
一方で、人間の感情や行動を扱う学問としては心理学が有名ですが、脳科学と心理学はコインの裏表、時計と時間のように切り離せない関係にあります。時計は時間がなければ存在し得ず、時間は時計がなければ測れません。同様に、脳科学がなければ心を測ることはできません。脳科学とはいわば、人間の心の変化を定量的に測るための方法論とも言えるのです。
分野を超えたネットワークで脳に迫る

医療・福祉分野に加え、経済や産業分野へと応用脳科学の研究領域が拡大している(出典:応用脳科学コンソーシアム 公式サイト)
───脳科学でいま最も注目されている研究について、教えて下さい。
人間の脳細胞の数は1千数百億とも言われますが、中でも知覚や記憶、情動などを処理する大脳が発達している点が、他の動物にはない大きな特徴です。近年、その働きが特定の部位だけでなく、それらをつなぐ神経ネットワークの同時多発的な作用で構成されることがわかってきました。
日常の何気ない会話1つを取っても、私たちは相手の言葉を聞いてその意味を理解するだけでなく、口調や表情、仕草、その場の状況の変化などを総合的にとらえ、瞬時に判断を下しています。それゆえ、こうした同時多発的な作用を理解するためには、脳科学に加え、心理学、生理学、行動科学、それに言語学や教育学、社会学、哲学や倫理学など、これまで個別に培われてきた知の統合が求められます。人間の生理現象や行動がすべて脳の指令によって引き起こされる以上、それにまつわる研究はすべて、脳のメカニズムを知ることにつながります。そもそも、脳を知ることは人間について知ること。だからこそ、あらゆる研究分野の連携が必要なのです。
MRI(磁気共鳴機能画像法)の原理を応用し、脳が機能しているときの活動部位の血流の変化(血流動態反応)などを画像化する装置。生きている脳内の生理学的な活性を測定し、視覚的に表現するニューロイメージングの最有力手段でもある。
ニューロビジネスが導く巨大変革
日本発、産学連携の脳科学プロジェクト

───日本のニューロサイエンスは現在、どのような状況なのでしょう。
10年前、日本では脳科学というと、医学領域のイメージがまだ根強い状況でした。しかし私自身、ビジネスに脳科学を取り入れる世界の潮流を目の当たりにして、大きな驚きを覚えました。多くの企業に脳科学の産業応用の実効性を説いて回りましたが、大方の反応は、そうすることでどう収益に結び付くのかがわからない、といったものでした。このままでは世界に後れを取ってしまうという危機感を抱き、産学の横断的な連携プラットフォームとして「応用脳科学コンソーシアム」(※1)を2010年に創設しました。
その大きな目的は、科学界と産業界が連携する学際的なオープンイノベーションの場をつくり出すこと。産業界にとって、脳科学の知見を導入することで即、新しい製品を開発できるわけではない。しかし、それが将来的な産業や社会のインフラになっていくことは間違いありません。一方で科学界について言えば、日本の脳科学者のほとんどは基礎研究者であり、一般的に見て、研究の産業応用にあまり関心がない傾向がある。だからこそ、学際的な場を設けて産学の連携を図ることによって、オープンイノベーションの場を作り出す必要があったのです。
幸いにして、何人かの業界トップ企業で活躍されていた方や日本の脳科学を代表する研究者の方から賛同を頂き、その方々のご指導、ご支援のおかげで創立9年目を迎え、現在は幅広い領域の研究者と企業が参加するR&D研究会とワークショップ、教育と人材育成を担うアカデミー、産学の人材交流と情報発信を行うネットワークの3本柱で活動しています。そして、脳科学に対する社会的な理解の深まりとともに、その成果が目に見える形で実用化され始めているところです。
───こうした精力的な取り組みの一方で、脳科学やその応用分野における、日本が持つ強みについて教えてください。
脳科学の社会的な認知に課題が残る一方で、日本の基礎研究には非常に優れたものがあります。特筆すべきは、研究者自らがその知見を社会に役立てようとする動きです。
その代表と言えるのが、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)脳情報通信総合研究所の川人光男所長による取り組みです。川人氏は自らスタートアップを立ち上げ、所内にクリニックを開設するなどして、ニューロフィードバック研究とその実践の融合を図っています。(※2)
また、世界有数の脳研究拠点である脳情報通信融合研究センター(CiNet)では、基礎研究分野における領域融合的な研究や産業応用研究の取り組みも行っており、同センターの西本伸志氏の研究成果を活用し、NTTデータグループと共同でビジネス化の取り組みなども進められています。(※3)
もちろん、実証に基づく研究を原則とする科学と、革新的な目標を想定して開発を進めていくビジネスとは、それぞれアプローチが異なります。しかし、これらの取り組みが先例になることで科学界と産業界が歩み寄り、開発と並行してエビデンスを追求する柔軟な姿勢が培われていくことを、私自身も願ってやみません。
脳科学のビジネス応用は始まっている
───このようにビジネスに脳科学を取り入れたり、脳科学の知見に基づいたビジネスを実践することで、どのようなメリットが期待できますか。
脳科学研究では、「社会脳」や「感性脳」と呼ばれる、人間の社会性や感性に関する研究が行なわれています。中でもビジネスへの応用が期待されるのが、これまで主観的、経験的に語られてきた事柄を客観的、科学的に理解できるようになる点です。
例えば購買行動に関するアンケートやインタビューなどでは、回答と実際の行動が合致しないことが問題視されてきました。その大きな要因としては、回答が行動後の主観的記憶に頼った方法論であり、意識していないことには答えようがないことが挙げられます。こうした問題に対して脳科学や心理物理学を上手に活用すれば、無意識で行われる意思決定段階から脳の反応を分析できるというわけです。
こうして人の嗜好や感情、行動が脳のどんな活動に由来しているのかが判明すれば、より的確かつ無駄のない商品やサービスの開発が可能になります。既に世界トップクラスのビジネススクールがカリキュラムに脳科学を取り入れており、脳科学はビジネスに必要な知識になりつつあります。また、脳科学は人材育成や組織の活性化にも大きな躍進をもたらすと考えられます。組織とはいわば、人間の脳と脳がネットワークを構築している状態ですから、その時々刻々と変化する関係性が解析可能になることで、経営組織のあり方もより正確で効率的なものへと発展していくでしょう。
それほどまでに、脳科学に基づくビジネス=ニューロビジネスには、今後の産業のあり方を大きく変える力があると考えられているのです。
異業種の民間企業と異分野の脳科学研究者のコラボレーションを推進し、応用脳科学研究とその事業活用を目指す、オープンイノベーションモデルのコンソーシアム。日本神経科学学会の協力の下、NTTデータ経営研究所が2010年に設立した。
研究所内に精神疾患の患者向けクリニックを誘致。診断にfMRIを活用し、患者の脳情報をフィードバックしながら学習を繰り返すデコーデッドニューロフィードバック(DecNef)によって、脳内の状態を改善する臨床応用研究を実施している。
fMRIなどを用いて動画広告の解析や評価を行うマーケティング支援サービス「NeuroAI® D-Planner」。西本博士とNTTデータ経営研究所、NTTデータの共同研究によって実用化され、サービスを展開している。
融合する「脳科学×AI」の行方
脳科学とAIの融合が導く未来ビジョン

───脳科学を巡る最先端の動向の中でも、脳科学とAIの融合を図る取り組みに注目が集まっていますが、これはどのような意味を持つのでしょうか。
人間の脳は複雑な神経ネットワークの相互作用で機能していますが、計測したパターンをAIで解析することによって、脳のメカニズムをモデル化する取り組みが進められています。多様な人の脳をモデル化することで、脳活動を逐一計測することなく、特定個人の感情や意思決定、さらにはその結果である行動の傾向などを、AIが予測できるようになるのです。
人間に囲碁で勝利したGoogleのAIプログラム「AlphaGo(アルファ碁)」(※1)の開発者であるデミス・ハサビス氏も、「これからのAI開発は脳科学研究の成果をさらに取り入れたものになる」と述べています。AI開発に脳科学の知見を導入することで、より人間にとって使い勝手のよいヒューマンマシンインタラクション(HMI)を備えたAIへの成長が見込まれます。そして、こうしたAIの進化がまた、さらなる脳科学研究を可能にします。このように脳科学とAIの知を融合することで、スパイラルアップの進展が見込まれています。
───今後、AIの活用とともに脳科学の産業応用を進めることで、企業の立ち位置はどのように変わっていきますか。
「脳の満足度」を基準に、産業構造の変革が起きる中で、企業のあり方自体が大きく変化していくでしょう。脳を知り、人間を知ることで、ビジネスがより科学的なものへと置き換わっていきます。これは間違いのない流れだと考えています。脳活動をモデル化し、AIが個別の嗜好や行動を予測できるようになれば、その人が心地よいと感じる味や服装、空間などを個別に予測し、3Dプリンターなどでその人専用のプロダクトやサービスを提供することも可能になるでしょう。20世紀型の画一的な大量生産・大量消費の仕組みに代わり、1人ひとりに最適化されたデジタルオーダーメイド型のビジネス、「マスパーソナライゼーション」と呼ばれる産業の時代が到来することが予測されています。
このように人間の特性毎に「脳の満足度を高める」取り組みは、製品やサービス以外の領域にも広がっていくでしょう。人は不快を感じるとアクティブな行動ができなくなりますが、その状況は企業の損失であり、社会の損失でもあります。人間の脳の働きをきちんと理解し、その人の個性に適した職場や働き方を提案できるようになれば、性別や属性による待遇の差や、心の病気の問題にも大きな改善が見込まれます。脳に関する科学的な知見の応用が、働き方改革や社員の健康増進の取り組みなど、企業の社会的な役割や立ち位置にも大きな変化を与えていくでしょう。
いまこそ「脳科学の使い方」を巡る議論を
───脳科学によって人間の意思決定の仕組みが解明される一方、それをビジネスに応用することについて、様々な場面で倫理的な判断が必要になると思われます。こうした倫理の問題を今後、どのように解決していけばよいでしょうか。
間違いなく言えることは、脳科学の場合もAIやロボティクスなど他の技術と同様に、「その技術をどのように使うか」が問われていくだろうということです。電気自動車メーカーのテスラや宇宙ベンチャー企業のスペースXの創業者として知られるイーロン・マスクも、人間の脳とAIの完全接続を目指すプロジェクト「ニューラリンク」(※2)を推進するかたわら、こうした技術の先行きを巡る冷静な議論の必要性に言及しています。
AI研究の世界的権威であるレイ・カーツワイルも、シンギュラリティの到来に先駆けて、AIが人間の感情を理解する段階が必ず訪れると予言しています。実際に、脳科学の知見を社会に導入する取り組みは、もはや現実のものになりつつあります。イギリス政府は、人々に間接的な形で働きかけ、自発的な行動を促す行動経済学の手法「ナッジ」(※3)を活用するための専門家チーム「ナッジユニット(正式名称:Behavioural Insights Team)」を立ち上げ、省エネ政策などにその知見を導入することで、一定の効果を挙げています。
こうした流れの一方で、漠然としたイメージやネガティブな未来の印象にとらわれてしまい、議論自体を避けようとするのはナンセンスです。技術の進展が見込まれる以上、理解を深め、早くから議論を始めておくことこそが必要ではないでしょうか。
※本取材内容は、『INFORIUM』9号「脳科学が拓く未来社会とビジネスの展望」の取材内容をもとに、加筆・再構成したものです。
Google DeepMindが開発したコンピューター囲碁プログラム。2015年10月、人間のプロ囲碁棋士に互先(ハンディキャップなし)で勝利した初のAIとなり、大きな話題を集めた。
イーロン・マスクが2017年に創業した、ブレインコンピューターインターフェース(BCI)の開発企業。脳内で考えたことを伝達するための体内埋め込み型AIチップの開発に取り組んでいる。
強制するのではなく、肘で軽くつつく(「nudge」)ように人々の行動を誘導する方法。男性用小便器の内側にハエの絵を描き、清掃費を劇的に減少させたアムステルダムの空港のトイレが好例とされる。