サーキュラーエコノミーとは
前回はデータ連携に必要なトラストの重要性について解説したが、今回は過去の連載でもキーワードとなっているサーキュラーエコノミーについて焦点をあてたい。サーキュラーエコノミーとは、これまでの経済スタイルである大量生産・大量消費・大量廃棄型のリニアエコノミーに対し近年欧州を中心に提唱されている経済の仕組みで、資源の効率的かつ循環的な利用を図り付加価値の最大化を目指す循環型経済のことである。資源循環だけでなく経済価値および社会的価値創出にも効果が期待されており、欧州の「持続可能な製品のためのエコデザイン規則」はサーキュラーエコノミー化に向けた具体的な取り組みだ。日本においても、2020年5月に策定された「循環経済ビジョン2020」や、2023年に経済産業省が「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定し、政府としても資源循環システムの自律化・強靭(きょうじん)化と国際市場獲得に向け、サーキュラーエコノミーの推進を図っている。
サーキュラーエコノミー化に向けた協調
政策が推進される背景として、日本が小資源国であり石油や金属をはじめとした鉱物資源を輸出に大きく頼っていることや、再生材について国内需要が乏しく海外へ輸出されていることが大きい。地政学リスクにより重要鉱物を確保できない事態は、サプライチェーンの持続性が失われることにつながり大きな経済損失を招きかねない。そのため、国内の再生材供給を高め廃棄物等を資源として最大限活用することで、経済活動の継続性のみならず新たな成長につなげていくことが日本としての課題である。前述の政策含め行政機関におけるリサイクル関連政策等、政府による後押しはされているが、サーキュラーエコノミーが市場として成立するか否かが論点である。推定市場規模は50~100兆円規模と目されているものの、実際に市場化するには、製品の再生可能性の向上、バージン材と再生材の価格、消費者のモチベーション、静脈における透明性の確保等を解決する必要がある。これらの課題解決には、製品自体の循環型設計や長寿命化の促進、再生材の価格優位性やインセンティブ、バリューチェーンにおける情報開示が求められ、自社のみならずバリューチェーンに参画するステークホルダー全体で、官民連携はもちろんのこと、企業間・業界で協同、協調したルール検討や取り組みがますます重要となる。次回は、これまでの連載を踏まえた今後について解説する。

その他の連載記事
脱炭素社会 生き抜くための指針(1)カーボンニュートラル実現に「新しい競争軸」
脱炭素社会 生き抜くための指針(2)蓄電池における資源循環の取り組み
脱炭素社会 生き抜くための指針(3)サーキュラーエコノミーと工場や都市の「スマート化」(前編)
脱炭素社会 生き抜くための指針(4)サーキュラーエコノミーと工場や都市の「スマート化」(後編)
脱炭素社会 生き抜くための指針(5)エネルギーの非化石化について

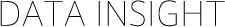



カーボンニュートラルについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/carbon-neutral/
環境についてはこちら:
https://www.nttdata.com/global/ja/about-us/sustainability/environment/