データ連携の重要性
これまでの連載にて、カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミーについて解説したが、どのテーマにおいてもデータ利活用の重要性が際立つ。データ利活用に取り組む企業は増加傾向だが、データ利活用による競争力強化やサーキュラーエコノミーへの対応は、自社データのみならずバリューチェーン上の関係各社のデータ連携が不可欠である。特徴的な動向として、2023年8月に発行された欧州電池規則ではバッテリのライフサイクル全体のCO2排出量の開示が求められる。また、デジタルプロダクトパスポートでは製品の生産・利用時の情報をデジタル情報として記録・共有を目指す等、自社の範囲を超えたステークホルダ間でのデータ連携を求める潮流を生みつつある。日本においても、2024年10月に発表された日本経済団体連合会の提言「産業データスペースの構築に向けて」では、競争力強化や環境課題解決に向け、データ連携の重要性が言及されておりデータ連携は加速すると考えられる。
データ連携に求められるトラスト
経団連の提言においても、組織間のデータ連携は、人、組織、モノのデータの真正性や完全性等のトラスト(信頼)の確保が必要であると言及されているが、いかにデータの不確実性を排するかが論点となる。取引契約にて取引先の信用、情物一致が明確であればトラストが課題化することはないが、取引契約の範囲を超えたユースケースや、異なる法規制環境にある企業とのデータ連携では、データの真正性や完全性が問われる。ライフサイクルで製品データを活用する場合、利用、回収、解体時のデータは製造者から見れば取引契約外のデータであり、信頼性を製造者だけで判定するのは困難である。確認行為を極力減らし効率的にデータを連携するには、自社における対策だけでなく、データを連携しあうコミュニティ内での改ざん防止、機密性担保、ルール制定等、データを連携しあうコミュニティで協調したトラストの仕組み整備が重要となる。まずは、データ連携の目的、必要なデータの特定、トラストを求める基準をコミュニティ内で共通認識化することがファーストステップとなる。「協調的なデータ利活用に向けたデータマネジメント・フレームワーク」(経済産業省)等各種ガイドラインも公表されているため、これらを参考とするのも一手である。次回はサーキュラーエコノミーを実現するための官民連携、業界協調について解説を行う。

その他の連載記事
脱炭素社会 生き抜くための指針(1)カーボンニュートラル実現に「新しい競争軸」
脱炭素社会 生き抜くための指針(2)蓄電池における資源循環の取り組み
脱炭素社会 生き抜くための指針(3)サーキュラーエコノミーと工場や都市の「スマート化」(前編)
脱炭素社会 生き抜くための指針(4)サーキュラーエコノミーと工場や都市の「スマート化」(後編)
脱炭素社会 生き抜くための指針(5)エネルギーの非化石化について

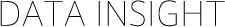



データスペースについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/dataspace/
カーボンニュートラルについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/carbon-neutral/
環境についてはこちら:
https://www.nttdata.com/global/ja/about-us/sustainability/environment/