- 目次
多くの企業においてサプライチェーン上流のGHG排出比率は高い
温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)の削減に向けて、パリ協定をはじめとする国際的な枠組みが形成されるとともに、国内でも制度整備の動きが進行している。
例えば、JPXはプライム上場企業を対象に、CO2排出量などの情報をTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に沿った形で開示することを求めている。TCFD提言は「ガバナンス」と「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」という4つ観点での情報開示を要求している。
「4つの中でも、ハードルが高いと見られるのが指標と目標です。ここではサプライチェーンを含めた企業活動によるGHG排出量の可視化、及び削減計画の開示が必要になります」と語るのはNTTデータの南田晋作である。
GHG排出量の可視化は容易ではない。排出量を算定する際の世界標準としては、GHGプロトコル(事業者排出量算定報告基準)が知られている。GHGプロトコルはScope1(工場・事業所、輸送などによる直接排出)、Scope2(電気や熱などの間接排出)、Scope3(サプライチェーンの上流・下流)という3つの分類を提示している(図1)。

図1:GHGプロトコル
さらに、Scope3は上流(カテゴリ1~8)と下流(カテゴリ9~15)に分かれている。計15カテゴリの中でも、取引先にとって特に重要なのが購入した商品・サービス(カテゴリ1)と資本財(カテゴリ2)である(図2)。
これらを可視化した上で、自社だけでなくサプライヤーや販売チャネル、さらには廃棄まで含めて排出量を減らす努力が求められる。

図2:GHGプロトコル Scope3
「例えば、鉄などの素材を製造するには大きなエネルギーを必要とし、CO2の排出量も大きい。下流の加工メーカーなどの注文に応じて、素材メーカーは工場を動かしています。素材産業だけが努力して解決する問題ではありません。サプライチェーン全体、さらにいえば社会全体で脱炭素に取り組むほかありません」と南田は話す。
Scope1・2は自社のことなので、比較的算出は容易だ。しかし、Scope3は他社への「お願いベース」で数値を入手する必要があり、可視化の難易度は格段に高まる。しかも、多くの産業においてScope3の比重は相当高い。
例えば、Cradle to Gate排出量(Scope1,2,3(上流)排出量)に占めるScope3のカテゴリ1・2排出量の割合をみると、建設業では76%に達する。同様に、食料品で93%、医薬品で78%、小売で76%、情報・通信業で68%。金属製品(22%)や金融・保険業(14%)のようにこの割合が低い産業もあるとはいえ、多くの企業はScope3カテゴリ1・2への取り組みなしに、実効的な脱炭素施策を検討することはできないのである。(※1)
SBT認定取得企業、RE100加盟企業、カーボンニュートラル宣言企業等122社の別に1社あたり平均排出量を算出。そのうえで取引先への開示が必要な組織レベルのCradle to Gate排出量(Scope1・2・3(上流)排出量)に占めるカテゴリ1・2排出量の割合を算出
何を買ったかではなく、誰から買ったかに注目する
まず、Scope3カテゴリ1・2の排出量を可視化する必要がある。そのための一般的な手法は、産業連関表ベースの排出原単位を用いている。産業連関表は国内産業間の取引関係を示す統計で、関係政府機関が合同で5年に一度作成される。この統計をもとにした製品・サービスごとの排出原単位を、各企業の活動量と掛け合わせて排出量を算定する。
例えば、PCを10台購入した企業なら、「PCの原単位×10台=PC購入に伴う排出量」。同じように、電池や複合機、工場の設備、部品などの物品、出張時の交通機関などのサービスについても算出し、すべてを足し算してカテゴリ1・2の排出量を可視化する。この手法の課題は「サプライヤーの削減努力を反映しにくいこと」だと南田はいう。
「産業連関表ベースの排出原単位は日本全体の平均値です。例えば、購入したPCのメーカーが特別な努力をして1台当たりのCO2排出量を大幅に低減させていたとしても、購入企業のカテゴリ1の値はほとんど変わりません。別の方法として、サプライヤーなどの取引先各社に対して、『製品・サービスごとのGHG排出量(カーボンフットプリント)を出してくれ』と依頼することはできます。ただ、すべての取引先にこれを要求するのは現実的とはいえないでしょう」
そこで、NTTデータが提唱するのが「総排出量配分方式」である。NTTデータは同方式を実装したソリューションとして「C-Turtle」(※2)を提供している。
「何を買ったかではなく、誰から買ったかに注目しましょう。それが、総排出量配分方式の考え方です。例えば、取引先A社の排出量(Scope1、2、3のカテゴリ1~8の合計)が100万トンで、売上高100億円としましょう。A社から1億円購入した企業は、1万トンの排出量を引き受ける形です。A社が削減努力の結果、排出量を50万トンに半減させれば、顧客企業は同じ1億円の購入でも5000トンだけを引き受けることになります」と南田。なお、総排出量配分方式はGHGプロトコルで認められており、環境省からも推奨されている。
サプライヤーの努力が、取引を介してダイレクトに自社のScope3に反映される。となれば、同じモノを買うなら「コストは大事だが、調達先の排出量も考慮しよう」という意識が働く。こうして自社の総排出量が減れば、その努力はサプライチェーンのさらに下流=顧客の総排出量を減らすことになる。サプライヤーにとっては、自分たちが苦労して排出量を削減した成果を顧客に還元できるということ。「お客さまのため」なら、削減に向けたモチベーションは大いに刺激されるはずだ。
「取引を通じて、誰かの削減努力がサプライチェーンに波及します。こうしたリンクをつくることにより、脱炭素化の努力を社会全体で共有する。それがC-Turtleの基本的な考え方であり、目指している方向です」と南田は語る(図3)。

図3:総排出量配分方式によるつながりの構築
組織レベルのCO2データ算出と製品レベルのCO2データ算出
総排出量配分方式を用いる際、その前提となるのが取引先各社の排出量(サプライヤー別排出原単位)と売上高の情報である。NTTデータは必要な情報を蓄積したデータベースを運用しており、これがC-Turtleの土台になっている。
「環境課題の解決に取り組む国際NPO(本部:英国)、CDPに対してGHG排出量を報告する企業は、日本でも増えつつあります。CDPに報告されたデータについて、NTTデータは日本で唯一プラットフォーム上に保持した上での算定使用許諾を得ています。CDPに報告していない企業については、NTTデータが個別に調べてデータベースを充実しています」と南田はいう。
サプライチェーンを上流に遡れば、企業規模が小さく、排出量の算定ツールなどの導入が難しい企業もあるだろう。その場合、算定値を必要とする大企業の協力のもと、一定の条件を満たした小規模企業にはC-Turtleを無償で提供するプログラムも用意されている。このプログラムを活用することで、大企業はサプライチェーン全体の排出量を高いレベルで把握することが可能だ。
いま、C-Turtleを導入して総排出量配分方式に切り替えるケースは、脱炭素に積極的なグローバル企業を中心に着実に増えている。
「日本の平均値としての排出原単位は2次データですが、サプライヤー別排出原単位は1次データ。この1次データを用いて各企業固有の排出量を可視化し、企業間のつながりを構築することでScope3を削減する。日本が2050年のカーボンニュートラルを目指すためには、こうしたアプローチが必須だと思います」(南田)
ただ、構築したつながりを生かして実質的な削減につなげるには粘り強い取り組みが必要だ。顧客という立場で、Scope3カテゴリ1・2の排出量算定をサプライヤーに強いることはできない。カーボンニュートラルの意義を説明しつつ、お願いし続けるほかない。
図4はサプライヤーエンゲージメントという考え方を示したもの。最初は、算定済のサプライヤーは一部にとどまるが、年単位の時間をかけて少しずつ取り組みに賛同するサプライヤーを増やしていくのである。

図4:サプライヤーエンゲージメントとは
「誰から買ったか」に注目するC-Turtleは、組織レベルのCO2データの算定方式である。1次データ排出原単位を把握する上では、もう1つの考え方がある。それが製品レベルでのCO2データ算定。製品・サービスのライフサイクルの主要プロセスを洗い出し、積み上げて排出路湯を算定する。
各製品のライフサイクル全体の排出量は、製品別カーボンフットプリント(CFP)と呼ばれる。それぞれのサプライヤーからCFPを入手できれば理想的だが、サプライヤーにとってCFP算出の負荷は課題だ。現状、CFPを算出している企業は多いとはいえない。
とはいえ、グローバルで事業展開する企業を中心に、日本でもCFPを算出し顧客に提供する事例が増えつつあるのも確かだ。背景にあるのが、脱炭素に熱心な欧州企業をはじめとする顧客側からのプレッシャーだ。そこで、NTTデータは製品別CFP算定基盤構築コンサティングサービスを提供しており、多くの実績を積み重ねている。
「ERPや工場システム、外部データなどをもとに、製品ごとの標準投入量などのデータを抽出して計算し、結果が妥当な値になっているかを確認します。アウトプットは工場別GHGや製品別CFP、Scope別GHGなど。顧客へのCFPデータ提供だけでなく、タイムリーな情報開示にも役立つ仕組みです」(南田)
一方、顧客側の立場では、中小企業を含むすべてのサプライヤーにCFPを求めるのは難しい。そこで、南田が提案するのがハイブリッド方式だ。
「サプライヤーのCFPがないと困る製品分野もあると思いますが、そうではない分野もあるはず。前者については粘り強くサプライヤーを説得しつつ、後者については総排出量配分方式を用いるというやり方もあるでしょう。特に複数事業を展開する企業は、こうしたやり方が適しているかもしれません」
NTTデータは、こうしたハイブリッド方式の仕組みづくりも支援している。
EU規制に対応する「C-Turtle CBAM」と金融機関向けの「C-Turtle PCAF」
以上、C-Turtleを中心にGHG排出量の可視化をサプライチェーン全体に広げるためのアプローチを解説した。NTTデータの関連ソリューションとしては「C-Turtle CBAM」、「C-Turtle PCAF」などのサービスもある。
EUは炭素国境調整措置(CBAM)という施策を開始している。製品づくりの過程で、排出したCO2が一定レベルを超えると関税をかけるという措置である。ポイントはCBAMがCFPとは異なること。CBAMでは、特定プロセスの実排出量が求められる。C-Turtle CBAMはこれに対応するソリューションだ。
一方のC-Turtle PCAFは金融機関向けのソリューション。投資先プロジェクトに伴うGHG排出量について、金融機関も一定の責任を負うべきとの主張は世界的に強まっている。PCAF(金融向け炭素会計パートナーシップ)は、こうした考え方に基づいて世界の金融機関が自主的に定めたルールで、日本でも参加する大手金融機関が増えている。
「例えば、1000トンのCO2を排出するプロジェクトなら、10%の株式を保有する金融機関に10トン分のCO2を引き受けてもらう。金融機関には株主としての影響力を生かして、投資先の脱炭素化を促してもらおうとの狙いです」と南田。C-Turtle PCAFはすでに提供されており、NTTデータには様々な金融機関から相談が寄せられている。
カーボンニュートラルへの道のりは長く、足元を確かめながら一歩ずつ前進する必要がある。その初期段階で取り組む必要があるのが可視化だろう。「可視化→削減→価値訴求」のサイクルをスムーズに回し続けるため、私たちは削減努力をつなぐC-Turtleをさらに進化させていきたいと考えている(図5)。

図5:脱炭素化の努力を社会全体でもっと共有するために

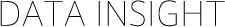



CBAM、PCAFに関連するホワイトペーパーはこちら:
問い合わせ先:
mis-mfg3-green@kits.nttdata.co.jp
あわせて読みたい: