- 目次
“NO”といわれた瞬間から、イノベーションへの旅路が始まる
イノベーターは「“NO”の国」に住んでいます。新しいアイデアや商品を提案すると、たちまちいくつもの“NO”に行く手を阻まれます。「そんなことは不可能だ」、「大事なことではない」、「そんなことをしている時間はない」、「予算がない」等々。
では、何がイノベーションを阻害しているのでしょうか。イノベーション創出手法を体系化した「FORTHイノベーション・メソッド」は15の障壁を定義しています。
- 1.過去の成功事例の束縛。「うまくいっているのに、なぜ変える必要があるのか」といった反対意見も含まれます。
- 2.多様性の不足。チームのメンバーが同じ考え方なら、イノベーションは期待できないでしょう。
- 3.失敗への恐怖。
- 4.文化的規範による制約。「これがウチのやり方だ」という規範は強力です。
- 5.官僚・官僚主義。
- 6.組織のサイロ化。部門間のコミュニケーションが希薄で、協働も起こりにくい。
- 7.リスク忌避。人は「新しいことをやるのはリスキー」と思いがちです。
- 8.変化への抵抗。
- 9.短期成果偏重。
- 10.経営者の目的と整合していない。
- 11.市場が見えていない。
- 12.実はイノベーションとか、どうでもいい。
- 13.イノベーション創出の方針が曖昧。
- 14.“イノベーションの起こし方”を知らない。
- 15.イノベーションに関する評価基準がない。

図1:イノベーションを阻む15のバリア
以上の15は主たる障壁であり、他にもいろいろあるでしょう。いずれにしても、イノベーターはいくつもの障壁を乗り越えて前進しなければなりません。それは困難な道のりであり、ときには感情を抑えきれなくなることもあるはずです。“NO”、“NO”、“NO”ばかりの相手に対して、怒りをぶつけたくなる気持ちは分かります。
しかし、“NO”を突き付けられて終了すればイノベーションは起こりません。イノベーション創出への旅路は、“NO”といわれたその瞬間から始まるのです。そのためには、まずあなた自身のマインドセットを変えなければなりません。
周囲の人たちが保守的になるのは当たり前です。それを受け入れ、理解することが重要です。イノベーションの障壁となっている上司や経営者を敵ととらえてはいけません。彼ら彼女らとつながり、引っ張っていく。そして、“NO”を“YES”に変えるのです。
経営者に「YES」といわせるための15の戦略
では、経営者の“YES”を得るために、どのようなアプローチが考えられるでしょうか。FORTHイノベーション・メソッドは15の戦略を提示しています。
- 1.経営アジェンダの理解(後述)。
- 2.イノベーション人材の育成。周囲の理解者や支援者を見つけ、そのネットワークをつくりましょう。ネットワークがあれば、お互いに支え合うことができます。
- 3.サイロを超えた“We”nnovation(後述)。
- 4.最強のチームをつくる(後述)。
- 5.経営・体験させる。
- 6.素晴らしいイノベーターになる。
- 7.イノベーションのスイートスポットをつかむ(後述)。
- 8.イノベーションを戦略に適合させる。
- 9.成功事例を紹介する。
- 10.イノベーション創出の伴走者を見つける。イノベーションは1人ではできません。
- 11.顧客中心主義。
- 12.“成果の実証されたやり方”を取り入れる
- 13.顧客のコミットメントを示す。「お客さまがこれを望んでいる」ということを認識させるのです。
- 14.イノベーティブなビジネスケースをつくる(後述)。
- 15.そのビジネスケースを売り込む。

図2:経営者に“YES”といわせるための15の戦略
15の戦略の中から、重要と思われる5つをピックアップします。「後述」と付記した1、3、4、7、12の戦略です。
1番目。経営アジェンダの理解、つまり経営者が何を重視しているのかを知ることです。少し変わったたとえ話をしましょう。知人が私にプレゼントを贈ってくれました。箱を開けてみると、そこにはイヤリングが入っています。私はイヤリングをしたこともなければ、したいとも思わないので、迷惑なだけです。
経営者の考えるアジェンダを理解していないと、同じことが起こります。イノベーションとして新規性を重視する経営者もいれば、収益性を優先する経営者、顧客体験を高めたいと思っている経営者もいるでしょう。経営者が何を重視し、どこにプライオリティを置いているのかを理解しなければなりません。
経営アジェンダの理解は、バリア10「経営者の目的と整合していない」の解消に有効です。
多様性豊かな最強チームをつくる
3番目の“We”nnovation。“I”nnovationではありません。イノベーションは1人で実行できるものではなく、チームで成し遂げるもの。あなたのめざすイノベーションにはどのような仲間が必要でしょうか。おそらく、研究開発やマーケティング、生産、ロジスティクス、営業、サービスなどさまざまな専門性を持つメンバーが集結する必要があるはずです。チームには10人いれば足りる場合もあれば、50人、100人を要するケースもあるでしょう。
サイロを越えた“We”nnovationは、バリア6「組織のサイロ化」を乗り越えるアプローチとして大きな効果を発揮します。
4番目の最強チームについて説明する前に、あなたがAさん、Bさんと一緒に苦労して画期的な製品を開発したと仮定してみてください。3人は新しい製品をいとおしいと感じ、「世の中の人たちに製品のよさを伝えたい」と思うでしょう。一方、大きな組織であれば、3人が開発に取り組んだことを知らない社員(例えば、CさんやDさん)もいるはずです。
新製品が発売されて初めてその存在を知ったCさんやDさんは、あなたたち3人と同じ熱量で製品を「売りたい」「もっと改善したい」と思うでしょうか。もし、CさんとDさんが開発プロジェクトに最初から参加していたなら話は別です。CさんとDさんは、3人と同じ“We”nnovationの仲間。きっと3人と同じくらいの愛情を製品に注ぐことでしょう。プロジェクトに対してすべてのメンバーが同じ気持ちを持つことができれば、そのチームは最強です。
プロジェクトには多様な人たちが参画しなければなりません。極端な考え、多くの人と異なる思考を持つメンバーも必要です。10人に2人くらいは、気難しい性格のメンバーもいたほうがいい。そして、変り者のメンバーであっても、チームにはその人物を受け入れる寛容さが求められます。同じ意見の人ばかり集まったのでは、議論をしても新しいアイデアは浮かんできません。
組織変革のスピードは、最も遅い者(部門)によって決定づけられます。チームに最も遅い者を巻き込むことで、イノベーションのスピードを高めるのです。最強のチームづくりは、バリア2の「多様性の欠如」への対策として効果的です。
“INNOVATORS”と“INNOWAITORS”
7番目は、イノベーションのスイートスポット。ほとんどの経営者は、何もしないリスクのほうが大きいとき以外、イノベーション創出に取り組みません。イノベーションに無関心な人は、組織の至るところにいます。
私たちは、世の中には2種類の人がいると考えています。“INNOVATORS”と“INNOWAITORS”です。多くの人が後者であり、イノウェイターとして待ちの姿勢を続けています(図3)。イノベーターは機を逃さず果実を手にすることができますが、イノウェイターはイノベーションが必要とされる時期に数歩遅れてしまうので、収穫を得ることができません。

図3:イノベーターとイノウェイター
経営者の意思決定の遅れにより、イノベーションの好機を逃すといった事例は山ほどあります。上司や経営者の決断を促すのもイノベーターの役割です。そのための方法はシンプル。不安にさせることです。
例えば、「競合の発表した新製品、すごいですよ」、「大口顧客に離反の兆候があります」、「ウチの商品は若者から飽きられ始めています」。一定のリアリティがあれば、経営者は「自社には何か問題がある」と感じ、「対策が求められる」、「イノベーションが必要だ」と思うでしょう。
経営者の抱いた不安の中心点が、イノベーションのスイートスポットです。ここを撃ち抜く説明やプレゼンテーションができれば、「実はイノベーションとか、どうでもいい」というバリア12を乗り越えられます。
12番目の“成果の実証されたやり方”を取り入れることも重要です。イノベーションは未知の領域であり、一種の探検プロセスです。そこにリソースを投入すべきかどうか、意思決定者がリスクを懸念するのは当然のことでしょう。
ただ、世の中には実証済のやり方があります。それはイノベーションプロセスのすべての旅程を照らすものではありませんが、いくつかの部分では大きな助けになります。リスクの低減は経営者の安心材料です。実証済みのやり方は、バリア14「“イノベーションの起こし方”を知らない」への対策として効果を発揮します。
世界で活用される「FORTHイノベーション・メソッド」
「FORTH」はSTEP1「Full steam ahead」(全速力でスタート!)、STEP2「Observe & learn」(観察と学び)、STEP3「Raise idea」(アイデアを出す)、STEP4「Test idea」(アイデアをテストする)、STEP5「Home coming」(帰還)の頭文字をとって命名された、実践的なイノベーションの方法論です。イノベーションのプロセスを、以上の5つのステップでサポートします。
STEP1では、まず決裁権者が最終判断の条件や方針を事前に提示します。そして、イノベーションの目的を定めます。イノベーションという探検を成功させるためには、明確な「目的地」が不可欠です。その上で、目的と整合するようチームを編成します。目的が変われば、チームのメンバー構成も変わります。
STEP2は観察と学び。さまざまな成功事例や技術などを学ぶとともに、ターゲット顧客の不満を集める。こうした情報が気づきにつながります。
STEP3では、発散と収束を繰り返すアイデア出しの方法論が活用されます。数百以上のアイデアを創出し、STEP1で定めた方針に基づいてチーム全員で議論。最終的には、15の新しいコンセプトを生み出します。
STEP4では、ターゲット顧客に対して、STEP3のコンセプトをテストします。コンセプトとアイデアが本当に通用するのかどうか、その検証が行われます。
STEP5で事業企画に落とし込みます。ビジネスモデルをつくり、新事業の企画書を作成。最終案をプロジェクトオーナーに提出します。

図4:FORTHイノベーション・メソッド
FORTHイノベーション・メソッドは世界各国の企業で活用され、多くの成果を生み出しています。NTTデータでも自社内での新規事業開発に導入しているほか、お客さまのイノベーション支援の一環としても、ワークショップの開催やファシリテーションのサービスなどを提供しています。
また、NTTデータはグローバルトップクラスの陣容のFORTH イノベーション・メソッド公認ファシリテーター認定者を擁しており、自社の新規事業に閉じることなくお客さまとの共創やイノベーション創出を促進する仕組みづくりの活用など、ユースケースが広がっています。
いま、多くの日本企業がイノベーションに取り組んでいますが、業界特有の固定観念から抜け出せない、あるいは気合と根性を強調するやり方なども散見されます。たまたまヒットが生まれたとしても、再現性がないため単発で終わってしまうケースも少なくありません。FORTHイノベーション・メソッドを活用することで、こうした課題を克服し、イノベーション創出の数やヒット確率を増やすことができる。日本での注目度も高まっています。

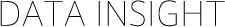



NTTデータの新規事業創発支援サービス詳細はこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/ida-bizdev/
ハイス氏の書籍「Breaking Innovation Barriers」詳細はこちら:
(本書Chapter12 “Apply Proven Methodologies” はハイス氏の依頼を受けた西村が著したものです)
https://www.amazon.co.jp/Breaking-Innovation-Barriers-management-buy/dp/9063697201
あわせて読みたい:
【第1回】新たなビジネスモデルによる新規事業の必要性と難しさ