提言、実装、さらに成果を追う
顧客のITシステム構築など、実装領域を強みにグローバル規模で存在感を発揮してきたNTTデータ。
2023年からコンサルティング力の強化に乗り出し「提言、実装、成果」というスローガンを掲げ企業変革を行っている。
NTTデータでコンサルティング事業本部長を務める池田和弘は「我々は国内外の様々なITサービスやシステムを手掛けるなかで、これまでも実装と共に顧客への提言を行ってきました。提言・実装を繰り返しながら、お客さまの事業課題を解決するためのケイパビリティを得てきたんです」と語る。

「これを礎に、顧客の経営課題に入り込み、成果へ直結するような提言や働きかけを強め、顧客のビジネスをより活性化する。その実現のためにコンサルティング力の強化を進めています」(池田)

この変革を推進するため、同社がまず目を向けたのが、組織体制の刷新や自社の強みの精査だ。
重厚長大な大企業を内側から変えるのは簡単ではない。しかし、池田は、NTTデータの強みの一つに「愚直さがあった」と語る。
「変革と言えばかっこよく聞こえますが、内実は愚直さが大事なんです。“ビジネスモデルの転換”ですから一歩一歩、積み重ねていかなくてはなりません」(池田)
個々人の社員が企業変革を自分事として捉え、素直な心で愚直に動くことができる。このカルチャーがあるからこそ、コンサルティング力の強化に同社は一丸となれているという。
「既存メンバーが最大限に潜在能力を引き出す意識を持つこと。また外部からの人材登用も積極的に行い『多様性』を重視しています」(池田)
それがチームとなり、ひいては企業を変えていく。顧客の経営課題の上流から伴走できるパートナーへと進化を遂げようとするメンバーに、池田は期待を寄せる。
成果への課題と、組織再編の実像
同社でグループ全体のコンサルティング力の強化と、ビジネスの拡大をミッションとしている安藤督は、20年以上にわたりNTTデータ一筋でキャリアを歩んできた。
安藤によれば、現状と目指すべき姿とのギャップを埋める最重要課題は「お客さまのビジネス成果へコミットする能力の質的・量的な拡大」にあるという。

同社はこの課題を解決するための一策として組織再編を実施。顧客の商品やサービスが市場に届くまでに、どのような過程を経ていて、どのような課題があるのかを見極められる組織へと再構築した。
顧客のバリューチェーンの機能ごとに、NTTデータが持つ専門性を発揮し、ベストプラクティスを提供することが狙いだ。
例えば、顧客のサプライチェーンに沿った業務改革に特化したチーム、エンジニアリングに専門性を持つチームなど、より成果を出すための強みを明確にした編成を組んでいる。
「従来のような『ITソリューションありき』のアプローチから脱却し、お客さまの業界動向や経営課題から議論を始める。その上で、必要なソリューションを組み合わせていく。このようなアプローチができれば、顧客のビジネス成果創出に向けて本質的な議論が可能になります」(安藤)

ただ、機能別組織への移行には、各組織が機能ごとの最適化に止まってしまうという新たな懸念もある。これに対して同社では、お客さまの経営課題を捉え、お客さまが企業としてどうあるべきかを描くために、NTTデータの総力を結集し、有機的に連携しながら、価値を提供していく姿勢だ。
これまで様々な業界を横断し、業務プロセスの改革、システム実装、さらには新規事業開発まで、一気通貫で支援できるケイパビリティを備えてきたからこそできる「NTTデータらしい価値のつくり方」だ、と安藤は強調した。
共創によって事業の蓋然性を高める
NTTデータの組織改革の要の一つを担うのが、顧客の新規事業開発を支援するビジネス&サービスデザインユニットの存在だ。
このユニットを率いる西村祐哉と岡田洋己は、大企業における新規事業開発を実践。その方法論の確立など、顧客の新規事業開発の糸口を生み出している。
「大企業の中にある多くのアセットやリソースを“使い倒し”ながら、いかに成功するための再現性を高めていくか。それを実践知としてお客さまに提供していくことが我々のミッションです」(西村)

同ユニットの特徴は、新規事業開発の機能を顧客の組織内に「インストール」することへのこだわりだ。
「我々が支援している間だけ新規事業が進むのではなく、お客さまの組織に仕組みとして定着させることが重要です」と岡田は強調する。

実際のプロジェクトでは、初期から外部の専門家を巻き込み、その実現可能性の評価を重ねるという。
「アイデアの評価だけでなく、お客さま自身がプロジェクトを実現するための実現可能性があるか裏付けを取ることを重視しています。これにより、新規事業の成功確率を高めることができます」(西村)
NTTデータ自身が大企業であることも顧客への提供価値につながっている。
「お客さまの新規事業創出に伴走するなかで直面する壁には、NTTデータがすでに経験しているものが多くあります。我々自身が経験値を蓄えながらそこで得た知見をお客さまに共有することで、顧客の新規事業における不確実性を下げ、再現性を獲得できるんです」(西村)
こうした取り組みを受け、池田は「ビジネスデザインユニット」という名称の由来とあわせて新規事業創出について説明する。
「新規事業をつくることは、白いキャンパスに輪郭を描くようなものです。どのような輪郭を描き始めるのか、どの点から打つのか、全体像でどんな絵になるのか。それらは“デザイン”といえます。時には一度はデザインしたものを捨てる作業が起きることもある。部署名に“デザイン”という言葉を冠した理由でもあります」(池田)

企業が事業ポートフォリオを変革し、成長モデルを描くためには、サービスやソリューションの再現性が欠かせない。さらに、そのビジネスの確度を高め、事業ポートフォリオに組み込める蓋然性も重要になる。
「新規事業への投資というのは、お客さまにとって大きなチャレンジです。だからこそ求められる蓋然性をいかに高めるか。NTTデータは企業間をつなぐプラットフォームをつくることや、外部パートナーと共創しエコシステムをつくることを得意としています。こうした知見を生かし、お客さま、あるいは外部パートナーも巻き込みながらともにチャレンジすることが、NTTデータの新たな価値提供であり、蓋然性を高めることにつながっていくと考えています」(池田)
多様性がもたらす新しい化学反応
着実に進捗する組織変革。組織変革の現場で、最も悩ましいのが「外部人材の統合」だが、同社の組織人材マネジメントユニットでは、この課題に正面から向き合っている。
「NTTデータの中で、本部長の池田など外部からジョインした人材が変革を推進する姿を見て確信しました。“外の血”を入れなければ会社は変われない」同ユニット長の三好寛は、外部人材登用の理由を語る。

この方針のもと、外資系コンサルティングファームで豊富な経験を持つ髙浪司が、副ユニット長として着任した。しかし、その道のりは平坦ではなかった。
「当時でも80人いるメンバーのマネジメントレイヤーに外部人材がすぐに就くことは、当社では前例のないケースでした」(三好)
この人事は組織内に大きな波紋を投げかけた。
髙浪は着任後、これまでの経験に基づく新たな規律やルールの導入を試みる。だが、その過程で組織内での軋轢も生まれた。
「私の当たり前は、メンバーにとっての当たり前ではない。丁寧なコミュニケーションの積み重ねなしには、新しい血の融合は難しいことを実感しました。現在は、互いが築いてきた考え方をすり合わせ、変えていくチャレンジを続けることで、一体感や新たな化学反応が生まれています」(髙浪)

その経験は、髙浪自身が「若輩者だった」と内省する一方で、次へつながる学びともなった。
「大規模システムを数多く手掛けてきたNTTデータだからこそ、社会課題の解決に応えられるようなケイパビリティを有しています。こうしたケイパビリティを持つ人材が経営課題に向き合うことの価値を私が世の中に広く伝えなくてはいけないと思いました」と髙浪は語る。
さらに「デジタル時代だからこそ“人の力で未来を変える”を私は信条にしています」と高浪は続ける。
規律やルールといったシステムが整っていても“人”の力がなければ企業変革は後押しできない。一人ひとりの力を信じ、人の個性に沿った成長支援を続けている。
この変革を俯瞰する池田は、「人的資本」という観点から重要な示唆を提示する。
「人的資本とは、単に人をコストではなく投資として捉えることだけではありません。多様な人材が持つ別の視点、経験、実績を融合させ、新しい価値を創造すること。それこそが本質的な意味です」(池田)
さらに池田は「地政学的視点」の重要性も強調。「シンプルに言えば『相手のことを知る』ということだ」と話す。
「自社の景色からだけでなく、相手の立場から物事を見て、理解し、提案する。組織人事においても、表層的な見方をせず、従業員の立場、ステークホルダーの立場、経営者の立場、それぞれの視点から考察することが不可欠です。だからこそ外部人材を交えた組織で、融合しながらビジネスをつくらなくてはいけません」(池田)
変革が導く未来は「日本企業」のために
NTTデータが推進する変革は、日本企業全体が直面する構造的な課題への解答でもある。池田は、その文脈で現状を分析する。
「日本企業の海外売上比率は過去20年で着実に上昇し、欧米企業に比肩するレベルに達しています。しかし、事業の多角化や多国化が進むなかで、利益率向上という課題が残されている。この課題解決には、経営とデジタルの両面からのアプローチが不可欠です」(池田)

具体的な指標として、ROE(株主資本利益率)が挙げられる。日本企業のROEは米国企業と比較して顕著に低く、8%という国際的な投資基準にも届かないケースが多い。この状況を打破するために、池田は「事業ポートフォリオの転換」を重視する。
「ROEを高めるには、売上高利益率の向上が不可欠です。そのためには、既存事業の見直しも含めた、大胆な事業ポートフォリオの転換が必要となる。この決断、特に『捨てる』という決断を、お客さまと共有できるパートナーでありたい」(池田)
さらにその先には、産業の枠を超えた新たな価値創造が待っている。同社は「社会変革プロデューサー」という言葉を掲げている。
現在、社会課題の解決には、一社では対応できない領域が増えている。例えば、カーボンニュートラルの実現に向けては、自動車産業やバッテリーメーカーなど関連職種だけでなく、関与する業界が俯瞰して青写真を描くことも肝心だ。
そこで必要になるテクノロジーは何なのか、いかなる産業と歩まなければならないのか……全体的な視点から考えるのもNTTデータの役割という意志が表れる。
「日本企業は今、大きな転換点に立っています。かつての製造業を中心とした成長モデルは、すでに限界を迎えています。新たな成長エンジンの確立には、事業構造の転換、グローバル市場での競争力強化、そして社会課題解決への取り組みが不可欠です」(池田)
「失われた30年」を経て、今こそ日本企業は本質的な変革に踏みださねばならない。
「我々は日本発の企業です。日本を元気にすると積極的に言っていこうと思っています。NTTデータが変革のパートナー、またはそのプロデューサーとなり、日本を元気にする役割を果たしたい。そのためには、ともに成長や挑戦をする仲間やパートナーをどんどん増やしていきたいと思います」と池田は力を込めた。
そこには、いち企業の変革を超え、日本の未来を見据えた決意が表れている。

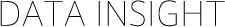



NTTデータのコンサルティングについてはこちら:
https://www.nttdata.com/jp/ja/services/consulting/
あわせて読みたい:
「事業変革の伴走者」になるための挑戦